ビックス・バイダーベック(コルネット&ピアノ)
Bix Beiderbecke (Cornet & Piano)

本名:レオン・ビスマルク・“ビックス”・バイダーベック Leon Bismark “Bix” Beiderbecke
1903年3月10日アイオワ州ダヴェンポート生まれ。
1931年8月6日ニューヨーククイーンズ区にて死去。
ビックス・バイダーベックは、かの油井正一に最も愛されたミュージシャンであり、油井氏が亡くなられてその葬儀の斎場には静かにビックスの奏でるコルネットが流されていたと言います。もちろんこれは故人の指示のもとだったのでしょう。
そんなビックスはその30年にも満たない短い人生で一体何を成し遂げたのでしょうか?粟村政昭氏はその著『ジャズ・レコード・ブック』において次のように述べています。「サッチモに支配されていたジャズ・トランペットの世界に初めてサッチモ以外の吹き方があることを示した偉大な先人」であると。ではこの「偉大な先人」について振り返って行きたいと思います。

油井正一氏の監修したビックス・レコード・コレクションの決定盤『ビックス・バイダーベック物語』(CBS SOPB 55017〜19)に拠りますと、彼の名声はポール・ホワイトマンのスター・プレイヤーだった時代(1927〜1929 中断あり)にミュージシャン仲間には確立されていたそうですが、大衆のヒーローではなく一般の人は誰も彼のことを知らなかったそうです。彼の名が一般に知られるようになったのは、女流作家ドロシー・ベイカー(Dorothy Baker:1907〜1968)が書いた1938年の小説「トランペットを持った青年(Young man with a horn)」がベスト・セラーになったことによるそうです。そしてその本の扉には「この小説は、ビックス・バイダーベックの創造した音楽に刺激を受けて執筆したものである。だが、ビックスの生涯を描いたものではない。」と記されていたそうです。著者のドロシーは、元々ジャズ・ファンでジャズに関する短編小説などいくつか書きそのキャリアをスタートさせていたそうです。その最初の長編小説が「トランペットを持った青年(Young man with a horn)」でした。当時女性のジャズ・ファンというのは珍しかったのではないでしょうか?ともかく僕はこの小説を読んでいませんが、主人公リック・マーティンの人生は、ビックスの人生に酷似しているそうです。
さてこのベスト・セラー小説は『情熱の狂騒曲』(邦題、原題は小説のまま)というタイトルで、1950年ワーナー・ブラザーズで映画化されます。主演はカーク・ダグラス、他にローレン・バコール、ドリス・ディ、ホーギー・カーマイケルらが出演しています。これは見てみたいなぁ。右は『情熱の狂騒曲』の1シーン。左がマーティン役のカーク・ダグラス、右はビックスと交流のあったホーギー・カーマイケル。
この小説のベスト・セラーは大きな影響を及ぼします。当時1938年はベニー・グッドマンが出現し、俄かにスイング・ファンが増加した時代でした。そして彼らはこう思います、「ビックス・バイダーベックって誰だ?」そしてそんな人たちはビックスのレコードを狂気のように探し回った(油井氏)そうです。こういった現象をレコード会社が黙って見過ごすはずがありません。7、8年間に廃盤にしていたビックスの入ったレコードを次から次と再発売します。こうしてビックスは巨人化され、伝説化されていくわけですが、そのおかげで現代のわれわれが彼の演奏に触れることができるので、ブームというのも場合によってはとても大切なことです。
しかしかつてスイング・ジャーナルの編集長を務めた久保田次郎氏は冷静に次のような見解を述べています。「ビックスを伝説化することには、黒人ジャズに対する反抗姿勢という意味合いもあります。いわゆるジャズ史上の巨人と言えば、キング・オリヴァーしかり、ルイ・アームストロングしかり、デューク・エリントンしかり黒人の名前ばかりが上がります。ちょっと待て、ビックスがいるだろうと白人たちは言いたくもなるのです。」実に的を得た指摘と言えると思います。

生い立ち
「ビックスの本名は、「レオン・ビスマルク・“ビックス”・バイダーベック」とどの本にも書いてある。しかしディヴ・デクスター・ジュニア氏はこれに異を唱えているそうで、彼が取材したところによると、バイダーベック家では、男子が生まれるとミドルネームに「ビスマルク(Bismark)とつけるのが習わしだったが、ビックスの父はこれを拒否し、”Bismark”ではなく”Bix”というミドル・ネームをつけた。拠って彼のフルネームは、レオン・ビックス・バイダーベック(Leon Bix Beiderbecke)が正しい」のだといいます。
さてこのビックスは、1903年3月10日アイオワ州ダヴェンポートで生まれました。このダヴェンポートという町は、ミシシッピ川に面していて、対岸はイリノイ州でロック・アイランド、モーリンという2つの町があり、この3つの町を総称して「三都市(The tri-cities)」と呼ばれているそうで、このダヴェンポートは商業都市であり、娯楽の町でもあったのだといいます。ショウボートは、ミシシッピ川を供船に押されたり引かれたりしながらニュー・オリンズから登って来て、ダヴェンポートに数日間停泊して興業を行いました。また「月光巡覧船(Moonlight cruises)」と呼ばれる定期遊覧船が5人編成のバンドとお客を乗せて、三都市を巡回営業していたそうです。
このダヴェンポートという町は1835年ジョージ・ダヴェンポート少佐によって開拓されましたが、そのごく初期の住人の中に既にBeiderbeckeというドイツ系の名前が見えるそうです。
ビックスの父親の名は、ハーマン・ビスマルク・バイダーベックと言い、「東ダヴェンポート燃料木材会社」という会社を経営していました。そして母アガサとの間にチャールズ、メリー・ルイズ、レオンという3人の子供がありました。バイダーベック家では、男の子が生まれると「ビックス」というアダ名をつけることになっていたそうで、レオンが生まれた時にはすでに兄チャールズが「ビックス」と呼ばれていたので、レオンは「リトル・ビッキー(little Bickie)」と呼ばれていたそうです。
バイダーベック家はまた、クラシックでなければ音楽ではないといった頑固な家庭ではなく、父親はよくギターを奏で、母もピアノやオルガンを奏することがあり、そんな折は「オールド・ブラックジョー」のようなフォスターの音楽が奏されていたそうです。
このようにビックスは音楽好きの一家の下で育ちましたが、彼は特に音楽に早熟な才能を持ち、耳も良く母親の話によると、3歳の時にピアノに手を伸ばして、1本の指で、リストの「 ハンガリア協奏曲 第2番」を弾いたそうです。彼はまた大変な恥ずかしがり屋で、よく誰もいない部屋でピアノを弾いたと言われています。ピアノが置いてある部屋に誰かいると絶対にピアノに触らなかったともいわれています。
しかしピアノの才能を見込んだ両親は、ことによったら将来コンサート・ピアニストになるかもしれないと期待に胸を弾ませ、1910年7歳の時に正式な教師をつけることにします。しかしその教師は1年で辞退してしまうのです。ビックスは耳がことのほかよく、聴いた曲は何でも完璧に弾きこなす、そのために面倒臭がって楽譜を覚えることをしなかったと言います。結局彼は、譜面を読めるようにはなりませんでした。そしてそのことは後に大きな禍根となるのです。

ジャズとの出会い
ビックスがジャズを知り、コルネットを手にするようになったのは、1918年15歳のころからだと言われています。そのきっかけは兄のチャールズが第一次世界大戦に従軍し除隊となって戻ってきます。その時兄は高級蓄音機と言われていた「ヴィクトローラ」を買ったのです(戦勝ボーナスでも出たのかな)。この当時は蓄音機を買うとオマケに数枚レコードが付いてきたそうで、その内の1枚か2枚が当時としては最新吹込みのO.D.J.B.(オリジナル・ディキシーランド・ジャズ・バンド)のレコードでした。これにビックスは魅了されたのです。
早速ビックスはこの年中古のコルネットを手にします。ビックスの叔父にアート・ピーターソンというバンド・マスターがいたので、コルネットを教えてくれるようお願いしますが、これはあっさり拒否されます。そこでビックスは、独学で、ヴィくとろーらだけを先生にコルネットを学び始めるのです。ビックスの楽器の取り扱い、吹奏法が正式でないのはそのためです。普通コルネットのヴァルヴで最もよく使うのは第1、第2ヴァルヴなのですが、ビックスは第3ヴァルヴを一番頻繁に使用します。この特異な指使いは一生変わらず、彼のユニークな効果はここから生まれた来たと言われています。
家族たちはビックスがヴィクトローラの前で胡坐をかき、レコードに合わせて吹いている光景をよく見たと言います。O.D.J.B.のレコードに耽溺して、ニック・ラ・ロッカのTpのメロディー・ラインを聴き覚えてヴィクトローラから出てくる音に合わせて演奏をしていたのです。時には回転を上げピッチを上げ、高いキーに直して同じ曲を吹いたりという練習をしていたそうです。
ビックスはダヴェンポート高校に入学しますが、音楽熱に取りつかれて他の何事にも頭を使おうとしないこの高校生に奇異のまなざしを注いだと言われますが、一方豊富なジョークで人笑わせ、スポーツ好きでもあったそうで、後のレイクフォレスト陸軍士官学校時代、野球チームの古いアルバムにユニフォーム姿のビックスの写真が発見されているそうです。「三都市」共催のテニス対抗戦で年代別のチャンピョンにもなっているそうです。運動神経と音楽の才能は比例するという説がありますが、比類ない音楽的才能の持ち主ビックスが比類ない運動神経の持ち主だったとしても不思議ではありませんね。

ともかく高校時代ビックスは三都市でもよされる音楽の集まりには必ず姿を見せたそうです。1920年リヴァーボート”ディキシー・ベル”に乗ってこの町にやってきたフェイト・マラブル楽団には、ルイ・アームストロングという当時20歳の青年が加わっていました。ビックスは彼の名を知らずにその演奏を聴いていました。
ビックスは、ニック・ラロッカのいるO.D.J.B.のレコードのようなディキシーランド・ジャズを演りたいと考えていましたが、なかなか同じような考えを持つ友人に巡り合えませんでした。それに彼の当時のレパートリーは、「フィジティー・フィート」、「オストリッチ・ウォーク」、「タイガー・ラグ」のわずか3曲だけでした。ラロッカには本当に傾倒していたらしく、ずっと後の1930年ごろあるジャム・セッションに参加したビックスは、ラロッカのエンディングを一音一音全てコピーして結んだそうです。そして最大のお気に入りは「タイガー・ラグ」でこれは終生変わらなかったようです。
またこの時代のビックスは、翌ダンス・パーティを訪れては加えてもらっていましたが、多くの場合レパートリーが極めて少なかったので邪魔者扱いされたそうです。彼の買ったコルネットはケースの付いていない中古だったため、新聞紙にくるんだコルネットを抱えて街を歩くビックスの姿は町の伝説となってしばらく残っていたそうです。
そして両親は、1921年18歳になり高校卒業が間近になったビックスが夢中になっている音楽に関しての心配は極まります。このままダヴェンポートに居ては本人のためにならない、ジャズを全く忘れるような環境にある学校に入れなければならない、そう判断した両親は、ジャズの中心地シカゴからわずか15キロのところにあるレイクフォレスト陸軍士官学校にビックスを入学させるである。ジャズに疎い両親はシカゴがジャズの中心地だということを知らなかったのです。こうしてビックスのレイクフォレスト時代が始まります。
しかし最近の研究によると、ビックスは1921年4月22日18歳の時、5歳の女の子に対して猥褻な行為をしたとして逮捕されます。両親が1500ドルという保釈金を払って保釈になり、起訴は行われなかったようです。この件については詳しいことはまだ明らかになっていないようです。しかしこのこともあって両親はビックスをレイクフォレストに入れたのではないかという推測されているようです。
レイクフォレスト時代
1921年9月ビックスはレイクフォレスト陸軍士官学校に入学します。この学校は週末を学生の自由時間に当てるという方針を取っていたため、毎週末ビックスはシカゴの黒人街サウス・サイドに通い始めます。ニュー・オリンズから移動した数多くのジャズメンたちがこの地でホットなジャズを演奏していました。O.D.J.B.のライヴァル、N.O.R.K.(ニュー・オリンズ・リズム・キングス)も「フライヤーズ・イン」に出演していて、ビックスは夜が明けるまでじっくり聴いていたそうです。
ビックは学業の方はからきしでしたが、コルネットの腕前はメキメキ上がって行きます。学生バンドを作り、体育館の映画のフィルム交換時間を利用して演奏したり、ダンス・パーティにも出演しました。ミュージシャンたちの間でビックスの顔は広くなりましたが、学業に対する熱意は全くなくなり、欠席数も増え、ついに落第してしまいます。そしてビックスは、音楽を一生の仕事にする決意を固めていました。「テラス・ガーデン」のバンドに加わっている時、プロとしてのユニオン・カードを手に入れようとしますが、テストの結果失敗します。

エメット・ハーディ(写真左)
CBSから出ている『ビックス・バイダーベック物語』(CBS SOPB 55017-19)の解説で油井正一氏は、「ビックスはレイクフォレストを退学して故郷に戻った」と自分から辞したように書いていますが、実際は学業不振と規律違反(寮に戻らない、飲酒)のため退学処分になったのです。どうも昔の評論家たちは物語をきれいにまとめようとする傾向がありすぎるように思います。
ともかく彼はレイクフォレストを退学となり、1922年夏ダヴェンポートに戻ってきます。母親は何とかしてビックスの願い、ユニオン・カードを得たいを叶えようと叔父でバンド・マスターをしていたアート・ピーターソン、この時はダヴェンポートでユニオンの資格審査委員をしていた、に頼み込んだ。ビックスは、コルネットではなくピアノで数曲のセミ・クラシックを弾いてなんとか合格したと言います。ビックスが心配していたのは、楽譜が読めないということで、実際楽譜に弱いことはこの後様々な局面で致命的になっていきます。
こうしてダヴェンポートに戻っている時に、エメット・ハーディという伝説のコルネット奏者と出会うのです。ハーディは、1940年アメリカの音楽評論家デイヴ・デクスター(1915〜1990年)が「ビックスを教えた無名のトランぺッター、エメット・ハーディー」という研究を発表して初めて広く知られるようになりました。日本では油井正一氏が紹介しています。
油井氏著『ジャズの歴史』によれば、ニュー・オリンズ郊外グレトナで生まれたエメットは、15歳でプロ入りし、リヴァーボートの専属バンドなど色々なバンドを渡り歩きます。そして19歳でニュー・オリンズ・リズム・キングス(N.O.R.K.)を経て、ダヴェンポートのカーライル・エヴァンス楽団に加入します。そこでまだコルネットに習熟していなかったビックス・バイダーベックに出会うのです。エメットは「彼こそ自分の後継者だ」と信じ、彼の手を取って吹き方を教えたというのです。
油井氏は、このエメット・ハーディと女性コーラスグループ、ボスウェル・シスターズの長姉マーサ・ボスウェル(Martha Boswell:1905〜1958)との恋愛物語も詳しく書いていますが、ここでは割愛します。

プロの道へ … ウォルヴァリン・オーケストラ
ビックスは1923年大学出身の仲間たちとバンドを結成します。「ウォルヴァリン・オーケストラ(Wolverine Orchestra)」です。写真右は1924年のウォルヴァリン・オーケストラ。右端はトミー・ドーシー、右2人目がビックス、右3人目がドン・マレイ(Cl)。
このバンドはシカゴとインディアナを中心に仕事を行いました。特にインディアナ大学で行う毎週末のパーティでの演奏は重要な仕事でした。当時インディアナ大学の学生の中に大変なジャズ・マニアがいました。その名はホーギー・カーマイケル(写真左)、『スターダスト』や『ジョージア・オン・マイ・マインド』の作曲者としてあまりにも有名ですが、俳優としても冒頭で触れた『情熱の協奏曲』や『ララミー牧場』など数多くの作品に出演しています。この時以来ビックスとホーギーは親交を結び、ホーギーはウォルヴァリン・オーケストラのために『リヴァーボート・シャッフル』を書いていますが、これをジェネットへの初吹込みで演奏しています。ウォルヴァリン・オーケストラは、24年中に16曲ほど吹込みを行ったそうです。

ウォルヴァリン・オーケストラの魅力は、何といってもビックス・バイダーベックにあったと言えるでしょう。このバンドにはニュー・オリンズ出身者が一人もおらず、全員が北部出身の白人でありながらディキシーを演奏した最初のバンドの一つとして伝説的な名声を得たと言われます。ビックスはコルネットばかりではなく、ピアノも弾きました。このバンドにはピアノにディック・ヴォイナウが記載されていますが、24年10月に吹き込んだ『ビッグ・ボーイ』では、ピアノのソロの部分はビックスが弾いています。
“ビックス”は、ピアノを弾きながら、新しいハーモニーを探求し続けました。幕間になると決まってピアノの前に座り、新しい音を作り出そうとしていました。晩年になるにしたがって、彼の興味はディキシーから印象派の音楽に移っていった。<イン・ア・ミスト>、<イン・ザ・ダーク>というピアノ曲は、そうした彼の探求心が生んだ珠玉の作品である。
ウォルヴェリンズは、1924年9月にニュー・ヨークのブロードウェイの中心タイムズ・スクエアにある「シンデレラ・ボールルーム」に出演し、センセーションを巻き起こします。ダンス・バンドと言えばスィート・スタイルか全く編曲に頼った音楽を演奏していたのですが、このバンドはジャズそのものを演奏したからです。それは“ビックス”がシカゴ時代にルイ・アームストロング、ジミー・ヌーン、ジョニー・ドッズなどの音楽に親しんで体得したフィーリングでした。

彼が終生の友として行動を共にする、フランキー・トランバウアー(写真右)と知り合ったのもこの時のことである。
油井正一氏は、「ウォルヴェリンズがまだシカゴで演奏していたころ、ジャズ史上ではもう一つ大きな出来事が進行しつつあった」とし、オースチン・ハイスクール・ギャングを中心とした白人たちによる黒人ジャズへの取り組みを挙げていますが、実はこの頃ルイ・アームストロングはシカゴを後にし、フレッチャー・ヘンダーソン楽団に加入するためニュー・ヨークに向かっていたのです。言いたいことは、「ジャズ史上ではもう二つ大きな出来事が進行しつつあった」ということです。ともかくここでは、シカゴの白人の若者たちに焦点を絞りましょう。
オースティン・ハイスクールに在学していた白人高校生を中心とする青年たちの一群が、やはりニュー・オリンズから来た黒人の巨星たちの演奏に目を見張って、聴き入っていたのです。そして彼らもまたやがて楽器を手に入れて演奏を始めるようになります。“ビックス”がウォルヴェリンズを作ったのはちょうどその頃でした。
ジミー・マクパートランド、バド・フリー・マン、エディー・コンドン、ジーン・クルーパ、フランク・テッシュメーカーらは、同じ人種から生まれた白人青年“ビックス”を英雄のように尊敬したといいます。中でも、ジミー・マクパートランドは“ビックス”の生き写しのようなスタイルを作り上げます。これがいわゆる「シカゴ・スタイル」と言われるものです。
ウォルヴェリンズが、“ビックス”以下O.D.J.B.に発する白人ディキシー・ランドを継承したのに対して、シカゴ・スタイルのミュージシャンはより黒人に近い線を継承しました。
1924年11月、”ビックス”はシンデレラ・ボールルーム出演中に退団します。彼一人が余りにも前に進み過ぎ、メンバーの考え方とかけ離れたことを知ったからだといいます。コルネットを失ったウォルヴェリンズは困り果て、先ずはニュー・オリンズから白人トランぺッターとして有名なシャーキー・ボナノを呼び寄せてオーディションを行います。シャーキーは、田舎の伊達男スタイルとしか形容できない珍無類の服装で到着し、メンバーをあきれさせたそうですが、彼の力強くヴォリュームのある音は、まるでバンドの独裁者のように聴こえ、余りにも釣り合いが取れないことから帰りの汽車賃を渡してお引き取り願ったそうです。
そうして“ビックス”のレコードから一音一音をコピーし、ビックス生き写しともいうべきシカゴのジミー・マクパートランドを後釜に据えたのでした。時にマクパートランドは17歳であった。
“ビックス”の抜けた後のウォルヴェリンズは、10か月後に解散の憂き目にあいます。ウォルヴェリンズがつぶれた時、ハスク・オヘアという男がスポンサーとない、残ったジミー・マクパートランドをリーダーとし、シカゴ・スタイルの若手、バド・フリー・マン、フランク・テッシュメーカー、フライド・オブライエン、ジム・ラニガンなどを加えた「ハスク・オヘアのウォルヴェリンズ」として再編したことが、シカゴ・スタイルの始まりとなっていくと油井氏のレコード解説は書いています。
<ゴールドケット楽団入団へ>

“ビックス”がウォルヴェリンズを辞めたのには目的がありました。デトロイトのビッグ・バンドであるジーン・ゴールドケットの楽団にに入りたかったのというのです。
しかしすぐには行かず一旦シカゴのチャーリー・ストレイト(Charlie Straight)の楽団にワラジを脱ぎます。
“ビックス”は、シカゴアンズと呼ばれる若手とは共演しなかったという見方をする人もいますが、油井氏はそれは違うといいます。ストレイト楽団にいた時に頻繁にシカゴアンズの面々と共演した記録が残っているといいます。しかしレコードの吹込みはありません。オースティン・ハイスクール・ギャング、シカゴアンズについては項を改めて取り上げていきたいと思います。
結局ストレイト楽団には1か月間しか在団しませんでしたが、ストレイト側では「世界一のトランペット奏者」を迎えた喜びもつかぬまで、実際起用してみると譜面に弱い”ビックス”にちょっと愛層をつかしたし、”ビックス”から見れば、自分をスター扱いにして給料をはずんでくれるのはありがたいが、その分他のメンバーの給料がカットされているのを見て辛くなったといいます(1か月で?アメリカは週給か)。
ともかくその後“ビックス”はセント・ルイスの「アルカディア・ボールルーム」のフランキー・トランバウアーの楽団に入ることになります。そこにはClのピー・ウィー・ラッセルもいたといいますが、なぜシャレではなくストレイトにジーン・ゴールドケットのバンドに入らず、チャーリー・ストレイト、フランキー・トランバウアーを経由したのかは記載がありません。
ここで油井氏が全く触れていない録音について触れておきたいと思います。1925年1月26日「ビックス・アンド・ヒズ・リズム・ジャグラーズ(Bix and his rhythm jugglers)」名義で吹き込まれた4面分です。リッチモンドにて録音されたというので、ジネット社への吹込みではないかと思われます。時期を考えると1924年11月ビックスはニュー・ヨークの「シンデレラ・ボールルーム」出演期間中に退団し、その後いつ入団したか記載はありませんがシカゴのチャーリー・ストレイトに1か月在団し、セント・ルイスに向かうので、タイミング的にはチャーリー・ストレイトを辞め、セント・ルイスに向かう間のことではないかと思われます。
この録音の中には年間ヒット・チャート73位にランクされるヒット曲”ダヴェンポート・ブルース”(Davenport blues)も含まれるのに全く触れられないのは不思議な限りです。
<ゴールドケット楽団時代>

セント・ルイスのフランキー・トランバウアーのバンドにデトロイトのジーン・ゴールドケットが「わしの傘下に入って、インディアナ州ハドソン・レイクでバンドを指揮しないか?」と誘ってきたといいます。フランキーは引き受けるのですが、その条件として”ビックス”も加えることを主張し、ゴールドケットはこれを受け入れ、フランキー、”ビックス”、ピー・ウィーはハドソン・レイクに赴いたと油井氏は記載しています。
しかしこの辺り話はちょっと不思議です。
“ビックス”はゴールドケットの楽団に入りたいためにウォルヴェリンズを辞めたのに、ゴールドケット楽団への加入はフランキーの<押し>で入っています。もしゴールドケットがフランキ−に誘いをかけなければ、またフランキーが押さなければ、そもそもフランキーが誘いに魅力を感じなければ、念願のゴールドケット楽団には入れなかったかもしれないのです。“ビックス”のゴールドケット楽団加入希望は、そんな他人任せ程度のものだったのでしょうか?非常に不思議だが僕には今のところこれ以上のコメントする判断材料は僕にはないので油井氏の記載を紹介するに留めます。
ところで、ジーン・ゴールドケットは、旅芸人の私生児としてフランスで生まれましたが、幼いころ一家でロシアへ移りモスクワの音楽学校で7年間学び、1911年(1910年という記載もある)に一家でアメリカへ渡ってきた移民でした。正規に教育を受けたためと彼自身の才能のおかげでクラシック・ピアノはうまかったといいます。このアメリカ移住はロシア革命に向かう政情不安がその原因かもしれません。
ジーンは、アメリカに渡ってほどなく新興の音楽「ジャズ」に大きな興味を抱くようになったといいます。彼がプロのミュージシャンとしてデビューしたのは、1914年シカゴの「ラムのカフェ」のクラシック・アンサンブルのピアニストとしてでした。その時はまだニュー・オリンズ生粋のジャズは知らなかったといいます。やがてデトロイトのクラシック・アンサンブルの楽長となりましたが、デトロイトに新しくできたダンス・ホール「グレイストーン」のバンド編成を委嘱されます。この頃から彼の仕事はバンド・マネージメント的な色彩が濃くなります。つまり各所に彼が掌握するバンドを複数作って売り込み始めたようなのです。元々クラシックのピアニストであった彼は、バンド・リーダーを別の人物に委嘱しました。例えば、後に独立してリーダーとなったラス・モーガンなども、24〜26年にかけて、このバンドの事実上のリーダーを務めています。そしてその後の事実上のリーダーはフランキー・トランバウアーが務めています。
油井正一氏によれば、ゴールドケット楽団は、ジャズ的な色彩を持ったコンサート・オーケストラという不思議なバンド・カラーを持ってデビューします。しかしビックスやトランバウアーの在団していた1926年の夏から1927年9月までは、名実ともに最高の白人ビッグ・バンドであったといいます。
ともかくハドソン・レイクでトランバウアーは、セント・ルイスから伴ったビックス、ピー・ウィー・:ラッセル、ソニー・リー(Tb)、イッチー・リスキン(P)、ダン・ゲーブ(B)、ディー・オール(Ds)とデトロイトから派遣された数人のメンバーでバンドを組織します。このことはエディ・コンドンの自叙伝にするされているそうです。

ハドソン・レイクはシカゴから75マイル(120キロ)、クルマで約2時間の距離だった。約1年間テッシュメーカーやコンドンはレイクへ、また月曜が休みだったビックスはシカゴに出て交友を深めたといいます。ビックスやピー・ウィーはこのようにシカゴアン達と親しく交友していたようです。
さて1926年の夏ハドソン・レイクの「ブルー・ランタン・イン」での仕事が終わります。ゴールドケットはトランバウアーにデトロイトの第1軍に合流するようしれを出します。そこでピー・ウィー・ラッセルら5名が脱落し、残りはデトロイトに向かいます。ゴールドケットは秋に行う東部ニュー・イングランドへの楽旅に際し、最強のチームを編成します。その時のメンバーは、
ジーン・ゴールドケット・アンド・ヒズ・オーケストラ(Jean Goldkette and his orchestra)
というものでした。このバンドは1926年9月25日ニュー・イングランドに向けて出発し、大成功を収めたといいます。
またこの時期重要なことに、正確な月日は分かりませんが1926年秋ジャズの歴史上に名アレンジャーとして名を残すビル・チャリスが正式にアレンジャーとして加わったことが挙げられます。
こうしてバンドは成功を収めますが、バンドは1927年9月24日の「ローズランド・ボールルーム」出演終了と共にゴールドケットの経営方針の変更によって解散されます。このゴールドケット楽団最後のステージとなった「ローズランド・ボールルーム」は、黒人バンドの雄フレッチャー・ヘンダーソンの楽団と白人サム・ラニンのスイート・オーケストラを雇っていましたが、ラニンのバンドは黒人のバンドと交代で出演することを快く思っておらず、特にヘンダーソン楽団に1924年ルイ・アームストロングが入団して、スイング感が画期的向上を遂げるといたたまれなくなりオリていました。そこにニュー・イングランドを席捲したゴールドケット楽団が乗り込んだのです。このことは当時のニュー・ヨークのミュージシャンの間で大変な話題となったといわれます。ミュージシャンたちが毎日のように足を運んで両バンドの対決に耳を傾けたといいます。当時ヘンダーソン楽団は、ストック・アレンジを廃し、天才ドン・レッドマンによるオリジナル・アレンジを演奏していて、「スタンピード」、「チャント」といった名作を吹き込んでいた時代です。そしてかたやゴールドケット楽団ではこれも鬼才と言われるビル・チャリスを擁していたのですから、聴きものだったに違いありません。
さてこのハイライトのバンド合戦を終えてバンドを解散したゴールドケット自身は、デトロイトの「グレイストーン」に出演して、ホットな演奏で観客を魅了していた黒人バンド、マッキニーズ・コットン・ピッカーズのマネジメントに専念するようになります。
ビックス・アンド・ヒズ・ギャング

ゴールドケット楽団が1927年9月24日に解散して、ビックスは10月31日に最大の白人ビッグ・バンド、ポール・ホワイトマンの楽団に入団します。油井正一氏は、9月25日から10月31日までの35日間が非常に重要だと述べています。それはこの35日間に初めて自己名義の録音を行ったからであると述べています。しかしこれは油井氏の誤りです。ビックスは拙ホームページ「僕の作ったジャズ・ヒストリー…初期のジャズ3-1925年」で触れたように、”Bix and his Rhythm Jugglers”名義で1925年1月26日4面分の録音を行っています。その内の1曲”Davenprt blues”は年間ヒットチャートに乗るほどのヒットを記録しています。
ともかくこの間にビックスやトランバウアーは、エイドリアン・ロリーニが集めたバンドに入り「ニュー・ヨーカー・クラブ」に出演していました。その時のメンバーは、
エイドリアン・ロリーニが集めたバンド、バンド名不詳
というものでした。確かに油井氏の言うようにビックスの”Bix and his Gang”名義の録音はこの時期初めてであり、またトランバウアー名義の録音にも参加しています。それらのメンバーの多くは上記ロリーニのバンドのピック・アップ・メンバーによって構成されていました。僕が不思議なのは、バンド・リーダーだったエイドリアン・ロリーニ名義の録音がないことです。
このロリーニのバンドの「ニュー・ヨーカー・クラブ」での反響は悪いものではなかったそうですが、経営者にとっては金のかかるバンドでした。さらに編曲者がおらず、グループとして見た場合まとまりに欠けるものがあったと言われています。ロリーニはチャリスにアレンジャーとして招聘しようとしますが、既にポール・ホワイトマンに引き抜かれていたのです。結局4週間の出演を行い10月29日に契約が切れます。そしてそれと同時にバンドも解散となります。
サックスのドン・マレイは、ゴールドケットがカンサス・シティで組んだバンドに加わり、エホラ、ディヴィス、ロリーニは大西洋を渡って、イギリスのアンブローズ楽団やフレッド・エリザルデ楽団に加わります。そしてビックスとトランバウアーはポール・ホワイトマンの楽団に加わったのでした。
この35日間を含めて1927年の録音については、「ビックス・バイダーベック 1927年」をご参照ください。
<ポール・ホワイトマン楽団時代>

ビックスがベースのスティーヴ・ブラウンと共にポール・ホワイトマン楽団に入団するのは、1927年10月31日のことです。フランキー・トラムバウアーは2週間遅れてシカゴで合流します。ビックスは早速ホワイトマン楽団の11月18日の録音から参加していますが、残念ながらこの音源は持っていません。ホワイトマン時代のビックスを振り返る前にこのホワイトマンという人物の動きを見ておきましょう。
ホワイトマンは1924年2月12日クラシックの殿堂、エオリアン・ホールでガーシュインの『ラプソディー・イン・ブルー』を初演が大成功を収め、アメリカ音楽界で確固たる地位を築きます。この辺りのことは、拙ホームページ「僕の作ったジャズ・ヒストリー…初期のジャズ2-1924年」をご覧ください。1926年11月ロス・アンゼルスに楽旅したホワイトマンは、パラマウントのヴォードヴィル・ショウに出演していた2人の歌手ビング・クロスビーとアル・リンカーを聴いて早速スカウトします。油井正一氏は、彼らは「リズム・ボーイズ」と名付けられますが、与えられたアレンジはリズミックではなく、翌27年ジョージ・オルセン楽団からハリー・バリスを引き抜いて加えてトリオとし、「リズム・ボーイズ」に対するヴィジョンが決まった、と書いていますが、別資料によればバリスは元々ピアニストで、ピアニストとして入団してから歌も歌えることから、ヴォーカル強化の意味合いからデュオに加え、トリオとしたとあります。
1927年4月にはレッド・ニコルスとファイヴ・ぺニーズを小切手帳を使って吸収合併します。しかし彼らはジミー・ドーシー以外は7月には退団してしまいます。そこで今度はゴールドケット楽団に触手を伸ばし、ビル・チャリスを手始めに次々とメンバーを引き抜いていくのです。我が国のある野球球団のようですね。因みにホワイトマンはビックス獲得については懐疑的だったそうですが、チャリスの説得がものを言いました。
これも油井氏によれば、ホワイトマンのバンドを毛嫌いする人は、「ホワイトマンのバンドはメンバーが多すぎるからジャズにならない」と言います。ホワイトマンのバンドは確かに常に20〜25人のメンバーを抱えていましたが、レコーディングに参加したのは大体12、3人で、全員揃うことは極めて稀だったのです。
ホワイトマンとヴィクターとの契約は1928年4月25日までで、ホワイトマンはコロンビアと交渉し、良い条件でコロンビアと契約を交わすことを口約束していました。ホワイトマンに契約更新の意思がないことを知ると、ヴィクターは契約期間内に出来るだけ多くの録音をことを計画しました。1928年1月4日から4月25日までに吹き込まれた曲数は少なくとも71曲、ことによると90曲にも及んだと言われます。何故推定なのかと言いますと、余りに録音し過ぎたヴィクターは1941年までそのすべてを発売することが出来なかったからです。録音から10年以上も経った音源はさすがに古臭くて使い物にならず結局多くの曲がオクラ入りになったということです。
ホワイトマンがヴィクターからコロンビアに移籍したことは、フォックス社のムービートーン・ニュースにもなったほどの話題となりました。しかしコロンビアに移籍したホワイトマンは、絶え間ないメンバーの入れ替えもあり、音楽的には振るわなくなってしまったと油井氏は述べています。
またこのころホワイトマンの楽団は次々と新しいアレンジに取り組み、楽譜を見てすぐに演奏する初見に弱いビックスは、新しい悩みに直面していました。そうしてビックスは深酒に陥るようになり、ついにはアル中になってしまいます。1928年暮、ホワイトマンはついにビックスに対して、給料は払うから十分に療養するように言い渡し、イリノイ州ドワイトの病院に入院させるのです。そしてその空席には、ビックスの模倣者アンディ・セクレスト(写真右)を雇って補充したのです。
 ビックスは1929年2月末にホワイトマンの楽団に復帰します。しかしアンディ・セクレストを気に入ったホワイトマンは、セクレストに第3トランペットの席を与え楽団内に留めます。このセクレストという人は「ビックスの模倣者」として日本の評論家の間ではすこぶる評判がよろしくないようですが、「ビックスの模倣」にかけては超一級だったようで、ビックスが不在中に吹き込まれた《ハウ・アバウト・ミー》におけるセクレストのソロは長年にわたってビックスのソロと信じ込まれていたそうです。
ビックスは1929年2月末にホワイトマンの楽団に復帰します。しかしアンディ・セクレストを気に入ったホワイトマンは、セクレストに第3トランペットの席を与え楽団内に留めます。このセクレストという人は「ビックスの模倣者」として日本の評論家の間ではすこぶる評判がよろしくないようですが、「ビックスの模倣」にかけては超一級だったようで、ビックスが不在中に吹き込まれた《ハウ・アバウト・ミー》におけるセクレストのソロは長年にわたってビックスのソロと信じ込まれていたそうです。
ビックスが戻ったその2月、ホワイトマンは、1回の出演料5,000ドルという好条件でコロンビア放送会社の「オールド・ゴールド」(タバコ会社)提供のレギュラー・ラジオ番組への出演契約にサインします。その他にブロードウェイのニュー・アムステルダム劇場で上演されていたレビュー、「ジーグフェルド・フォリーズ(Ziegfeld Follies)」、さらに同じくエディ・キャンター(Ededie Canter)出演のミュージカル「フーピー(Whoopee!)」への出演が重なり、さらにレコーディングも行わなければなりません。これはかなりの重労働が強いられることになります。油井氏によると、ラジオ番組だけでも毎週の放送のために準備される新曲は16〜20曲、編曲者も高級をもらいましたが、もちろん密度の高い編曲ができるはずがありません。読譜に弱いビックスは、再び酒に親しみ、健康を害していくのです。
油井氏はこの時期(1929年4月17日録音)にレコーディングされた『家に帰らないかい(Baby won't you please come home ?)』(「ビックス・バイダーベック 1929年」収録)について次のように述べています。「この曲でもファンの多くを惑わせている。ここには療養を終えて戻ったビックスとセクレストの2本のコルネットがいるのだが、ラストの数小節に至るまで、2本のコルネットは同時に出ない。どっちがビックスかをはっきり断定し得る人はいないのである。セクレストのような二流のニセモノと判別することさえ難しくなったほど、彼のプレイは生彩を失っていたのである。」
<映画『キング・オブ・ジャズ』>
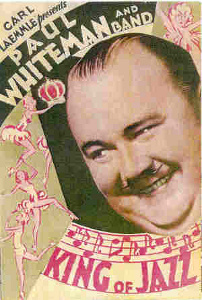
ホワイトマン楽団はニュー・ヨークで5月16日の録音の後、映画「キング・オブ・ジャズ」出演のため、特別列車を仕立てて「オールド・ゴールド」の費用で、金色に塗り立てた客車を連ねてハリウッドに向かいます。
映画会社は、デンヴァー・シンフォニーのセカンド・ヴァイオリニストであったホワイトマン青年が、全世界のスター「キング・オブ・ジャズ」になっていく伝記を作るべく交渉を進め、マネージャーもOKを与えていました。この自叙伝映画をホワイトマン自身が主役を演ずるというものでしたが、ホワイトマン自身はハリウッドに着くまで知らなかったというのです。映画は6週間で完成されることになっていましたが、ハリウッドに着いてこの話を聞いたホワイトマンは大いにゴネるのです。何が気に食わなかったのかは記載がありませんが、ホワイトマンは企画の根本的改正を要求し、映画会社は折れて要求を飲まざるを得なくなります。
企画と脚本が出来上がるまで、ミュージシャンは図らずも費用の一切をスタジオもちで、一人一台ずつフォードが与えられ、週1回の放送を除いて、まるで仕事はなく予想もしなかった豪華な休暇を満喫することになります。航空氏の免許を持つトランバウアーとビル・ランクは空を飛び、ビング・クロスビーとビックスはゴルフに興じ、ハリー・ゴールドフィールドとロイ・バーギィ―はトランプで日を送ったと言います。
ホワイトマンとその楽団員は、こうして3か月近くブラブラと過ごしていましたが、8月30日にオープンするニュー・ヨーク郊外での契約を履行するために、脚本が出来上がらぬまま一旦ニュー・ヨークに引き上げることになります。もし予定通り撮影が行われていれば、この映画を通じて我々はビックス・バイダーベックの演奏に接することができたはずでした。しかしビックスはニュー・ヨークに戻った直後再び健康を害し故郷のダヴェンポートに戻って養生することになるのです。
映画『キング・オブ・ジャズ』は、やっと企画を整え、11月1日にクランク・インすることになり、楽団は10月28日のレコーディングの仕事を終えた後再びハリウッドに向かうことになります。しかしこの間に全米中を大きく揺るがす一大事件が起こります。1929年10月24日それまで天井知らずの好況を謳歌していたウォール・ストリートの株式市況が大暴落を起こすのです。それはこの後5年以上にわたる大不況時代の幕開けでした。僕は見ていないのですが、油井正一氏によれば、このような動揺期に作られた映画『キング・オブ・ジャズ』は惨憺たる出来になってしまったそうです。ダヴェンポートで療養中だったビックスは当然映画には出演していません。
ダヴェンポートで療養していたビックスがニュー・ヨークに戻ってきたのは、翌1930年の4月の終わりのことでした。ニュー・ヨークに戻ったビックスに声をかけたのは親友の親友ホーギー・カーマイケルでした。彼は、オールスター・編成でビッグ・バンドを編成し、5月21日にヴィクターに2曲吹き込みます。トミー・ドーシー、ベニー・グッドマン、ジミー・ドーシー、バド・フリーマン、ジョー・ヴェヌーティー、エディ・ラング、ジーン・クルーパといったスターたちとともに、その午後のビックスは幸福そうに見えたといいます。
この時吹き込ん2曲は、「バーナクル・ビル・ザ・セイラー(Barnacle Bill , the sailor)」と「ロッキン・チェア―」(Rockin' chair)で、「バーナクル・ビル・ザ・セイラー」においてビックスは張り切った1コーラスのソロとっています。しかし「ロッキン・チェア―」の方は会社の方針でビックスではなく、ババー・マイレイが吹いているそうです。油井氏はこれが残念そうですがマイレイのこのソロは極めて貴重だと思われます。マイレイは初期のデューク・エリントンのサウンドを作り上げた天才の一人で、ビックスの没した翌年32年5月29歳という若さで天に召されるのです。
ディスコグラフィーによれば、ビックスはその後6月6日、アーヴィング・ミルズの名義<Irving Mills and his hotsy-totsy gang>というバンドで、3曲「ラヴド・ワン」、「ディープ・ハーレム」「ストラット・ミス・リジー」の録音に参加しますがいずれも未聴です。この録音について油井氏は全く触れていませんが、あまり出来が良くなかったのでしょうか?
そして不況のあおりを受けさすがのポール・ホワイトマンも、編成を縮小せざるを得なくなり、もはやビックスは必要とされなくなってしまいます。それはジャズ自体がこの世から必要とされなくなり、スイートな音楽が全盛を極めていたからでもありました。
ビックスは、世話をしてくれる友人のツテで、カサ・ロマ・オーケストラに入団することができます。そしてこの楽団には、ゴールドケット時代の友人も残っていました。しかし精緻を極める編曲者ジーン・ギフォードの楽譜は、楽譜の苦手なビックスにとって、まったく手に負えぬもので、わずか4日間で辞めてしまったと油井氏は書いています。ギフォードがカサ・ロマ・オーケストラに参加したのは1929年、その年からアレンジャーとして辣腕を振るい出します。自分の思い通りの精緻なサウンド創りに取り組み出したばかりのギフォードにとって、読譜の苦手なビックスは邪魔な存在だったのかもしれません。
またビックスがニューヨークに戻った直後、ヴィクターから、ピアノ・ソロを吹き込まないかという話もあったそうですが、何かの都合でその企画は最終的には、ビックスをリーダーとするレコーディング・オーケストラによるレコーディングに変わっていきます。ともかくビックスは人選に取り掛かり、親友たちを集め、1930年9月8日にレコーディングは行われます。しかし八方美人的なビックスはクラリネット奏者を3人も集めてしまうということもあったようです。
誰からも愛されたかったビックスは、「アイル・ビー・ア・フレンド」という曲をベニー・グッドマン、ジミー・ドーシー、ピー・ウィー・ラッセルをそれぞれ起用しテイクを3つ録ります。そのうち発売されたのはベニーとジミーのもので、ピー・ウィーのテイクはオクラ入りとなってしまいました。
ビックスがこの世に残したラスト・レコーディングは、1930年9月15日ヴィクターへ行われたホーギー・カーマイケル名義のオール・スター・セッションでしたが、ジャック・ティーガーデン、ジミー・ドーシー、バド・フリーマンといった豪華な顔ぶれでしたが、油井氏によれば結果は惨めなものだったとのことです(未聴)。
ビックスは高給を得ていたホワイトマン時代に、少なからぬ貯金を銀行に預けていました。しかし1929年株価暴落と銀行の取り付け騒動でその銀行が破産し全くの無一文になってしまいます。このことがビックスの健康をさらに害することにつながります。
1930年11月ビックスは仕方なく故郷のダヴェンポートに戻ります。イギリスの音楽誌「メロディ・メーカー」の11月12日付けのニュー・ヨーク通信には、「ビックス・バイダーベックは再び故郷のダヴェンポートに戻った。理由と期間は明らかにされていない」という記事が掲載されているそうです。
その年の暮れから翌1931年の春にかけて、ビックスの姿はダヴェンポート付近のナイト・クラブに見られたそうです。そうしたクラブの一つにイリノイ州ミラン(ダヴェンポートの対岸)にある<ブラックホーク・ウォッチタワー>という店がありました。そこに出ていたバド・ディヴィスというバンドに客演したこともあったそうです。しかしやる気になる前は、ただ黙りこくってパイプをくゆらせ座っていたそうですが、リーダーのディヴィスが彼の気を引こうと、大きな声で「次の曲は『タイガー・ラグ』(ビックスの最も愛した曲)をやろう!」と怒鳴ると、ビックスは慌てて「わあ、やるのかい」と言ってテレながら加わったそうです。
1931年 最後の年

1931年2月の初め、ビックスは再びニュー・ヨークに現れます。贅肉がつき一見して不健康そうだったと油井氏は書いています。どういう経緯か不明ですがチャールズ・プレヴィンの指揮するラジオ放送NBCの「キャメル・プレジャー・アワー」(油井氏は<キャメル・キャラヴァン>と書いているが誤り。<キャメル・キャラヴァン>の放送が始まるのは1933年)のオーケストラに加わり数か月を過ごしますが、ある日遅れてスタジオに入るとすでに代役が自分の席に座っていました。つまりはクビになったのです。
ある晩クラブでせがまれるままコルネットを手に取り、「スイート・スー」を吹き始めますが、途中で続けることができなくなります。最も得意な曲の一つ「スイート・スー」すら忘れてしまったのです。
ある日ベニー・グッドマンとウィリアムズ・カレッジに出た時のことです。ビックスは途中でいろいろな出来事がありすっかりくたびれていたといいます。「アイ・ガット・リズム」でビックスのパートに差し掛かりましたが、ビックスのコルネットからは音が一音を発せられませんでした。コルネットも吹けるBGがとっさに駆け寄りビックスのコルネットを吹き急場をしのぎましたが、それ以来BGとビックスは再び会うことはありませんでした。
このようなことが重なりビックスはクイーンズ区46丁目のアパートに引き籠り、一人でピアノを弾いて過ごすことが多くなります。そんな折プリンストン大学からビックスを含めたピック・アップ・バンドの出演を求めてきたといいます。どこに求めてきたのでしょうか?エージェントに加入していたのでしょうか?よくわかりませんが油井氏の記述によります。真夏でしたが悪性の風邪をひいて寝込んでいたビックスは代役を指名したところ、大学側からビックスが出ないならバンドもすべてキャンセルと言ってきたのだそうです。これに対して真夏のキャンパスが締まっている時期にパーティーがあるはずがないという指摘もあるそうですが、油井氏は伝記にそう書いてあると先に進めます。ともかくこれを聞いてビックスは奮起するのです。ニュージャージーにあるプリンストンまで、華氏100度(摂氏37.78度)の酷暑の中オープン・カーを走らせるのです。ダンス・パーティもうだるような暑さの中で行われました。そしてその帰途オープン・カーで涼んだのが良くありませんでした。数は急性肺炎に進み、46丁目のアパートで、ビックス・バイダーベックは28歳の生涯を閉じるのです。
ビックス・バイダーベック最後の章なので全体的な評を挙げておきましょう。
 先ず油井正一氏
先ず油井正一氏
「ビックス・バイダーベック物語」解説の最後を次のように結んでいます。「ルイ・アームストロングは既に60年に及ぶジャズの王座を保ち続けている。デューク・エリントンもまた40年を超すキャリアを持って活躍を続けている。ビックス・バイダーベックがプロとして働いたのは、わずか8年間に過ぎない。だが、アームストロング、エリントン、チャーリー・パーカーとともに、21世紀にも語り続けられる偉大なミュージシャンであることに変わりはない。『シンギン・ザ・ブルース』のワン・コーラスだけでも不滅なのである。」蛇足だがこういうところが僕が油井氏を信頼できないところなのです。この文の記述した時期は1964年となっています。1964年の60年前からサッチモが活躍しているとすれば1904年です。サッチモは1900年生まれなので、これに従えば4歳の時からジャズの王座についていることになります。氏は勢いというかその時の気分で書き散らす傾向があるように見受けられてならないのです。ジャズマンはその時の気分で上気しようと気分が乗らないこともわかりますが、評論家は冷静さを失うべきではないでしょう。
また僕はどうしてもジャズ史上に残る傑作と言われるこの『シンギン・ザ・ブルース』の素晴らしさが分からないのです。何度聴いても分からないのです。油井正一氏はこの演奏を「傑作」、「ジャズ史上に残る」と声高に吹聴していますが、録音周りについて何も触れていません。この傑作が吹き込まれたのは1927年の2月でビックスは、ジーン・ゴールドケット楽団に在団中だったはずです。どのような状況で吹き込まれたのか、別テイクはあるのかといったことです。ブライアン・プリーストリー氏によれば、この時代テイクは必ず2つ取り、テイク2をマスターとするのが通常だったといいます。もしそうならば別テイクが存在すると思われるのです。
またそれほど素晴らしいと言いながら何が素晴らしいのかまったく語っていません。フレッチャー・ヘンダーソンがレックス・スチュアートに一音一音模倣させてレコーディングしたとか同時代のミュージシャンはこのソロをみな暗唱したとか、ビックス好きでこのフレーズを記憶していない人はいないなど周辺情報は多いのですが、一体何がどう素晴らしいのかを全く語っていないのです。
続いてガンサー・シュラー氏
「バイダーベックの音楽家としての人生はあまりにも短く、余りに混乱しているため、業績の全体像を描くことは不可能である。そして早死にのおかげで、突然コルネット領域での英雄的な業績の報告で彩られた伝説的人物に仕立て上げられてしまった。しかし、彼の録音のみを基にしても、ビックスは、ジャズ・エイジの音楽外的な病理症状をもとにして創り上げられた伝説的な人物の域をはるかに超えるに値する人物であった。彼は、あらゆる時代に通用する真に偉大なジャズの音楽家の一人と呼ばれることにふさわしい。」
僕の最も信頼する評論家粟村政昭氏は、「サッチモに支配されていたジャズ・トランペットの世界に初めてアームストロング以外の吹き方があることを示した偉大な先人」と述べていますが、これにも少しばかり違和感を感じます。
というのはビックスがその素晴らしいプレイ”Singin' the blues”、”I'm coming Virginia”は1927年の吹込みです。一方ルイの最高傑作とされる”West end blues”は1928年の録音、ただルイの場合ホット・ファイヴ時代の1925年から時代を先取りする革新的なプレイをしていましたが。つまりルイのアンチ・テーゼとしてビックスが登場したのではないということであくまでも同時代人だったということです。
ただ若きビックスがサッチモに入れ込み、ベッシー・スミスに小遣いの大半をチップとして渡すという黒人ジャズへの傾倒ぶりを示しながら、自分のプレイは全くの正反対のものであったということは一体どういうことなのでしょうか?僕は彼はサッチモやベッシーの凄さ、本物感を知りながら一番心酔していたのは、自身でも語っているようにO.D.J.B.のニック・ラロッカだったのではないかということです。たぶん彼にはジャズを変革しようなどという気はさらさらなかった、大好きなディキシーランド・ジャズ(白人による)をやりたかっただけなのではないでしょうか?僕にはそんな風に思えてなりません。
レコード・CD
“Bix Beiderbecke/His best recordings 1924-1930”( Best of jazz 4012)
『ビックス・バイダーベック物語』(CBS SOPB 55017〜19)
”Bix and Tram 1928”(Swaggie S 1269)
「ベニー・グッドマン秘蔵名演集」(PDTD-1046)
 ビックスは1929年2月末にホワイトマンの楽団に復帰します。しかしアンディ・セクレストを気に入ったホワイトマンは、セクレストに第3トランペットの席を与え楽団内に留めます。このセクレストという人は「ビックスの模倣者」として日本の評論家の間ではすこぶる評判がよろしくないようですが、「ビックスの模倣」にかけては超一級だったようで、ビックスが不在中に吹き込まれた《ハウ・アバウト・ミー》におけるセクレストのソロは長年にわたってビックスのソロと信じ込まれていたそうです。
ビックスは1929年2月末にホワイトマンの楽団に復帰します。しかしアンディ・セクレストを気に入ったホワイトマンは、セクレストに第3トランペットの席を与え楽団内に留めます。このセクレストという人は「ビックスの模倣者」として日本の評論家の間ではすこぶる評判がよろしくないようですが、「ビックスの模倣」にかけては超一級だったようで、ビックスが不在中に吹き込まれた《ハウ・アバウト・ミー》におけるセクレストのソロは長年にわたってビックスのソロと信じ込まれていたそうです。













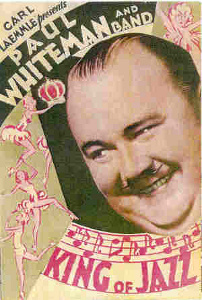

 先ず油井正一氏
先ず油井正一氏