ベニー・グッドマン 1935年
Benny Goodman 1935
[スイング時代は1935年ベニー・グッドマンとともに始まった。]と言われる。
 つまりこの1935年という年はジャズ年表上、ベニー・グッドマンによって一つの時代を画する「スイング・イーラ」、「スイング時代」の幕が開いた年であるということであろう。こうなるとBGの1935年というよりも「僕の作ったジャズの歴史」で取り上げるべき内容と言える。ここは淡々とBGの活動を追っていき、その影響その他については「僕の作ったジャズの歴史」で取り上げよう。
つまりこの1935年という年はジャズ年表上、ベニー・グッドマンによって一つの時代を画する「スイング・イーラ」、「スイング時代」の幕が開いた年であるということであろう。こうなるとBGの1935年というよりも「僕の作ったジャズの歴史」で取り上げるべき内容と言える。ここは淡々とBGの活動を追っていき、その影響その他については「僕の作ったジャズの歴史」で取り上げよう。
こういう言い方をすると、ベニー・グッドマン(以下BG)がスイングの生みの親みたいに聞こえるかもしれないが、もちろん音楽的にはそうではない。ではなぜこのような言い方をされるのか?このベニー・グッドマンの1935年から探っていこう。
1934年BGは、最初のレギュラー・バンドを組織してビリー・ローズのレストラン・シアター、「ザ・ミュージック・ホール」に出演することになる。この出演は6月から約3か月後の10月まで続いた。しかしこの時の演奏について油井正一氏によれば、世評は散々なものだったが、BGにとってはそれが次のステップに繋がることになる。その次のステップ、ラジオ番組出演となるのですが、その経緯についてはちょっとばかり記述が異なる点があるのでご紹介しておこう。
相倉久人氏は、「さてそのクラブの出演契約満了の日、広告代理店の男が新たに始まるラジオ番組のオーディションの話を持ってきました」としているのに対して、グッド氏は『1934年10月に「シアター・レストラン」の仕事が終えてから間もなくして…』と書いている。まぁ余り大した違いではないが。(写真は1935年12月23日クリスマス・ショウでのBG楽団)
その番組とは、ナショナル・ビスケット・カンパニー(略してナビスコ)をスポンサーとして、ラジオ・ネットワークの最大手NBCが企画したニューヨーク時間で土曜の夜10時30分開始の3時間の音楽番組。出演バンドは3組、ザビア・クガートのラテン・バンド、ケル・マレイのソサエティ・オーケストラ、そしてBGのバンドだった。各バンドの持ち時間は約1時間弱、毎週それだけの時間をこなすには相当なレパートリーが必要となる。
そこで登場するのがフレッチャー・ヘンダーソン。ヘンダーソンはその当時、「バンドが経営に行き詰まって解散したばかり」(相倉氏)、「バンドは仕事がなく、マネジメントのまずさもあって、解散に瀕していた」(モード氏)。ともかくヘンダーソンは、編曲の売り渡しに同意し、新たな編曲も手掛けることになった。しかしこれにはある人物がフィクサーとしてかかわっている。ビリー・ホリデイの初レコーディングとBGを結び付けたりとプロデューサーとしてグングン力を付けてきたジョン・ハモンド氏である。
こうして1934年12月1日ラジオ番組『レッツ・ダンス』が、BGの演奏するテーマ曲に載って、全米に向けて放送を開始し、翌1935年5月25日まで続くのである。BGにとってこのラジオ番組出演は、1935年後半に起こる熱狂的なBG人気を下地を作ったという意味で非常に重要な出来事となった。
BGは「『レッツ・ダンス』放送中の1935年1月と2月に、コロンビアに8曲を録音したが、その演奏は日増しに充実していった」とグッド氏は書いている。まずは、スイング時代幕開け直前、BG人気沸騰直前に吹き込まれたコロンビアへの吹込み(僕は2曲しか持っていないが)から聴いていこう。しかしその内の1曲はBG名義ではなく、イギリスの作曲家でピアニストのレジナルド・フォーサイスのレコーディングに参加したもので、グッド氏はこの曲を含めて8曲としているのかどうかは分からないが。

<Date&Place> … 1935年1月15日 ニューヨークにて録音
<Personnel> … ベニー・グッドマン・アンド・ヒズ・オーケストラ(Benny Goodman and his orchestra)
前回1934年11月26日からの移動
Trumpet … アート・シルヴェスター ⇒ ラルフ・ムジロ
Drums … サミー・ウェイス ⇒ ジーン・クルーパ
<Contents> … 「新たなる宝庫・黄金時代のベニー・グッドマン」(Columbia CSM 890〜1)
record2 A-4.[ブルー・ムーン](Blue moon)
ロレンツ・ハートの作詞、リチャード・ロジャース作曲の今でもよく取り上げられるいわゆるスタンダード・ナンバー。歌手のヘレン・ウォードはBGファンにとってはかなり有名な歌手。一時期BGと恋愛関係にあり、結婚寸前までいったが、結婚までは至らなかった。その原因を油井正一氏は、1936年ころBGは、思いのたけを打ち明けて結婚してくれと迫ったのだが、振られてしまった。変に真剣に思いのたけを打ち明けたりせずに、クラーク・ゲーブルやジェイムズ・ギャグニーのように、彼女の髪の毛をわしづかみにしてグイグイ引きずり回していたら(中略)。とにかくヘレンはBGを振り切りバンドを去って行ったと書いている。しかしウォード自身の告白によると、BGは自分のキャリアのことを考えて、つまりキャリアにプラスにならないと考えて求婚を断念したのだと話しているという。こういった人間臭いエピソードは面白いですよねって、僕だけ?でもどっちが本当なんだろう?何の根拠もないですが、僕にはウォードの言っていることが本当のような気がする。
肝心の演奏ですが、BGのソロもほとんどなく、いかにもこの時代の雰囲気を漂わせる、ソフトでビロードのような柔らかさを感じさせるアンサンブルとヴォーカルを楽しむナンバー。アンサンブルをリードするのはトロンボーンで、後のトミー・ドーシーを思わせる。ヴォーカルのウォードは当時まだ21歳のはずだが、その歌いっぷりには”初々しいセクシーさ”というよりも、”熟女的なセクシーさ”を僕は感じてしまう。

<Date&Place> … 1935年1月23日 ニューヨークにて録音
<Personnel> … ザ・ミュージック・オブ・レジナルド・フォーサイス(The new music of Reginald Foresythe)
<Contents> … 「新たなる宝庫・黄金時代のベニー・グッドマン」(Columbia CSM 890〜1)
record2 A-1.[ダッジング・ア・ディヴォース](Dodging the divorcee)
この吹込みはBG名義ではなく、作曲・編曲家でピアニストでもあるレジナルド・フォーサイスというイギリス生まれの音楽家の率いるバンドとBGバンドともコラボのような形で吹き込まれたもの。フォーサイスはフランスやハワイなどを渡り歩いてアメリカにやって来たという変わり種。非常にいろいろなタイプに興味を抱くような好奇心旺盛なタイプの音楽家だったと思われる。30年代から種々の木管楽器を用いて斬新な響きを追求していたと言われる。この録音について語られた記事をほとんど見かけたことはないが、後にエディ・ソーターをアレンジャーとして招いたり、ストラヴィンスキーやバルトークと共演したりと新しいサウンドに取り組むBGの創造性と合致して行われた重要なセッションのような気がする。
パーソネルについてもレコードのライナー・ノートにはほとんど触れられていませんが、クラリネットにBGの他にジョニー・ミンスという人物が加わっています。この人とバスーンのソル・シェーンバックそしてピアノの御大フォーサイスはフォーサイス側、他はBGバンド側からの参加ではないかと思われる。ここでもリズム・セクション以外はすべて木管で金管のトランペットなどは加わっていない。アンサンブルはクラシックを彷彿とさせる中にジャズっぽいフレーズもあり実にユニークなものである。
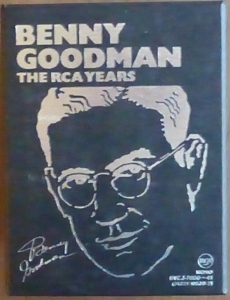 今回からは、ヴィクターに移籍してからの録音を取り上げていこう。
今回からは、ヴィクターに移籍してからの録音を取り上げていこう。
モート・グッド氏は、「1935年初めころコロンビアへの録音は、アーヴィング・ミルズによって大幅な制限を受けた。報酬は当時の慣行通り―均一価格で、レコード印税もなかった」と書いている。どうしてミルズ氏はそのようなことが出来たのだろう?そしてどうしてそのような制限を設けたのだろう?僕には確かめようがないが、グッド氏はそう書いている。
一方RCAヴィクターの社長だったテッド・ウォーラーシュタインは、アーティストに対して非常に尊敬の念を抱いていた。彼の哲学には、アーティストは、レコードの売れ行きに準じて継続的に印税を受け取るべきだという一項が含まれていた。ヴィクターの重役たちは、その考えに抵抗したが、BGとウォーラーシュタインは友人だったこともあって、その条件を入れてBGはRCAと契約した。これがジャズ・アーティストにとって初の印税が与えられるようになった大きな転機であるという。野口久光氏も、この契約はジャズメンとして初めての印税方式よるものだったと書いている。こうしてジャズメンにとって大きな転機となる契約が1935年3月に取り交わされたのだった。
さて、そのヴィクターにBGは1939年まで専属契約を行い多数の吹込みを行っているが、その音源の全曲集が今回からしばらく取り上げることになる左のCDボックスである。
これは、日本ではBMGビクター株式会社から発売された「コンプリート・ベニー・グッドマン」というもので、多分アメリカで発売された“Benny Goodman The RCA years 1935-1939”の日本盤CD12枚組という結構大型のボックスものである。日本側の解説は野口久光氏が書いていてこのCDボックスを「RCAの専属アーティストとして吹き込んだ全曲集である」と書いているのでそうなのであろう。
そしてアメリカ盤でも付いているかどうかは分からないが、「ベニー・グッドマン秘蔵名演集」というCDが付いている。このCD は資料としては大変な優れもので、17歳の時ベン・ポラック楽団で行った初吹込みから1930年のビックス・バイダーベックとの共演まで、他ならどうやって入手したらいいか分からないような貴重な音源を収録したCDが付いている。まぁ拙HPではすべて紹介しつくしましたが…。
こうしてBGはヴィクターと契約が成立し、初録音が4月4日、24丁目スタジオで行われた。この時点ではまだ、ラジオ番組「レッツ・ダンス」は放送中である。
 こうしてヴィクター時代に入るのだが、この時代はBGにとってどういう時代かというと、ずいぶん前に紹介した油井正一氏の『生きているジャズ史』のBG―三期説によれば第二期に当たる。
こうしてヴィクター時代に入るのだが、この時代はBGにとってどういう時代かというと、ずいぶん前に紹介した油井正一氏の『生きているジャズ史』のBG―三期説によれば第二期に当たる。
曰く
「第二期は、1935年に始まり絢爛たるビクター時代を経て、コロンビアに鞍替えした1939年ごろまで『キング・オブ・スイング』の盛名をほしいままにしたころ。技巧といい、フィーリングといい、非の打ち所のない立派なスタイルですが、第3期に至って完成を見る音色の豊麗さには、幾分欠けます。これが戦前戦後のビクター盤のフル・バンドとコンボを通じて、皆様におなじみのグッドマン・スタイルです」と。「皆様におなじみの〜」という表現が時代を感じさせますよね。今どきBGに馴染んでいる人というのはどのくらいいるんだろうか?
さてそんな高価そうなCDボックスが買えたなと思われる方が多いかと思う。現時点で帯が見当たらず定価で幾らだったのかは分からないのが、町田のディスク・ユニオンで3,000円を少し超えるくらいで購入した。多分今の日本ではベニー・グッドマンといってもほとんど「?」というくらいであろうし、そもそもボックスものは重いし嵩張るので嫌われるという当世の志向の反映かと思う。

<Date&Place> … 1935年1935年4月4日 ニューヨークにて録音
<Personnel 基本形> … ベニー・グッドマン・アンド・ヒズ・オーケストラ(Benny Goodman and his orchestra)
1935年1月15日からの移動。
Trombone … ジャック・レイシー ⇒ ジョー・ハリス
このヴィクターへの初吹込みを基本形とし、以後は移動のみを表示していくことにしよう。
<Contents> … 「コンプリート・ベニー・グッドマン」(BMG BVCJ-7030)
| CD1-1. | ハンカドーラ | Hunkadola |
| CD1-2. | アイム・リヴィン・イン・ア・グレート・ビッグ・ウェイ テイク1 | I’m livin’ in a great big way take1 |
| CD1-3. | アイム・リヴィン・イン・ア・グレート・ビッグ・ウェイ テイク2 | I’m livin’ in a great big way take2 |
| CD1-4. | フーレー・フォー・ラヴ テイク1 | Hooray for love take1 |
| CD1-5. | フーレー・フォー・ラヴ テイク2 | Hooray for love take2 |
| CD1-6. | ディキシーランド・バンド | The Dixieland band |

ベニー・グッドマン・アンド・ヒズ・オーケストラのヴィクター移籍初録音。このセッションに立ち会ったジョン・ハモンド氏は、これまでと違った“くぼみをつけたワックス盤”に記録され、その結果はより忠実度の高い録音になったことを後に語っている。またハイミー・シャーツアーは、その録音時ピアニストのフランク・フローバの足を踏み鳴らす音を消すために、彼の足の下にパッドを入れたことを思い出話に語っているという。なお、この「コンプリート・ベニー・グッドマン」の楽曲解説は野口久光氏である。
初吹込みは会社側の意向で当時の新作映画の主題歌が取り上げられた。CD1-1.「ハンカドーラ」は「スキャンダルス35年(George White's scandals of 1935)」のCD1-4,5.「フーレー・フォー・ラヴ」は「青春万歳(Hooray for love)」の主題歌であるそうな。
CD1-1.[ハンカドーラ]
BGのソロから始まり、BGが大活躍する時代を感じさせるナンバー。いかにも白人のスイング・バンドといった演奏だと思う。
CD1-2,3.[アイム・リヴィン・イン・ア・グレート・ビッグ・ウェイ]
テイク1と2が収録されている。この内テイク2がSP盤で発売されたもので、テイク1は初お目見えだというが、BGのソロが若干異なるだけでほぼ変わりはない。ヴォーカルを取っているのは、これまで何度か登場したディック・クラークである。僕が注目するのは、出だしの4小節が終わって、5小節目からホーンがメロディを1小節吹くと答えるようなフレーズをブラスが1小節吹くところで、これはまさにコール&レスポンスの手法で、ベニー・カーターがフレッチャー・ヘンダーソン楽団で行ったアレンジに似ている。今聴くと何ら新鮮味もないがこうしてアフリカン・アメリカンの手法がアメリカン・ポップスに浸透していったのだなぁと思う。
CD1-4,5.[フーレー・フォー・ラヴ]
映画の主題歌でヘレン・ウォードが歌っている。こちらもテイク2がSP盤で発売されたもので、テイク1は初お目見えだという。この曲のヴォーカルを聴くとヘレン・ウォードという女性は結構キツイ強い性格の娘だったのではないかと感じるのでありました。ソロは大将のBG。
CD1-6.[ディキシーランド・バンド]
これもウォードの歌入り。バーニー・ハニゲン(曲)、ジョニー・マーサー(詞)の曲でコロンビア系列のブランズウィックに吹き込んだばかりだという。他社に吹き込んだばかりの曲を直ぐ追っかけで録音するのは通常御法度なのだが、この時はヴィクターがブランズウィック専属だったテディ・ウィルソンの吹込みにサイドマンとして参加するという条件で吹込みがOKになったという。こうまでしてヴィクターがこの曲を録音したかったのは、BG自身はこの曲を気に入っていたわけではなかったが当時ヴィクターのA&R部門の長イーライ・オバースタインがこの曲を”ヒット曲”と考えていたからだという。

<Date&Place> … 1935年4月19日 ニューヨークにて録音
<Personnel> … ベニー・グッドマン・アンド・ヒズ・オーケストラ(Benny Goodman and his orchestra)
前回1935年4月4日(基本形)からの移動
Trumpet … ラルフ・ムジロ ⇒ ネイト・ケイズビアNate Kazebier
Trombone … ジョー・ハリス ⇒ ジャック・ティーガーデンJack Teagarden
Guitar … ジョージ・ヴァン・エブス ⇒ アラン・リュースAllan Reuss
<Contents> … 「コンプリート・ベニー・グッドマン」(BMG BVCJ-7030)
| CD1-7. | ジャパニーズ・サンドマン | The Japanese sandman |
| CD1-8. | あなたは天使 | You’re a heavenly thing |
| CD1-9. | レストレス | Restless |
| CD1-10. | オールウェイズ | Always |

初録音から約2週間後の4月19日に第2回目の吹込みが行われた。グッド氏は、「ジャック・ティーガーデンが加わっている。彼は、ブロードウェイのパラダイス・レストランに出演中だったポール・ホワイトマン楽団で演奏していた。彼は録音当日に参加しただけだった―そしてビッグT(ティーガーデン)がBGのヴィクター・バンドと共演したのはこの時だけであった」と述べティーガーデンの参加が注目点としているが、野口氏は、CD1-7,8がフレッチャー・ヘンダーソンの、CD1-10はフレッチャーの弟ホレスの、CD1-9はヘンダーソン・スクールの優秀なアレンジャー、スパッド・マーフィのアレンジの初吹込みであることが注目としている。さすが野口氏の指摘の方が重要だと思う。グッド氏が注目するティーガーデンはCD1-8「あなたは天使」と次曲CD1-9「レストレス」で短いソロを取るだけで、演奏自体にそれほど影響はしていないような気がする。野口氏の解説を読んで、演奏を聴くと確かに前回セッションと比べてグッと良くなった気がする。
CD1-7.[ジャパニーズ・サンドマン]
タイトルは日本人である我々には気になるところであるが、以前にも登場したことがあり当時はなぜか”ジャパニーズ・サンドマン”がやって来て砂を撒くと眠くなるという言い伝えがあったという。ヘレン・ウォードのヴォーカル入り。
CD1-8.[あなたは天使]
この曲もヘレン・ウォードのヴォーカル入り。ティーガーデンがアンサンブルをリードし、ソロはBGの後Ts、BG、As、Pが短いソロを取る
CD1-9.[レストレス]
冒頭やわらかいサックスのアンサンブルの後ウォードのヴォーカルとなる。ティーガーデンが短いソロを取る。
CD1-10.[オールウェイズ]
ヴォーカルなしのインスト・ナンバー。BGのソロ後アンサンブルとなり、短いティーガーデンのソロが入りアンサンブルに戻る。

先ず右の写真の説明から。右上をよく見ると、”Elitch's 1935”とあり、左上に”Benny Goodman's Let's dance band”とある。後列マイクの右がBG、左がヘレン・ウォード、前列右から4人目がバニー・ベリガンなので、”レッツ・ダンス”放送中でバニー・ベリガンが加わった時の写真と思われる。
ヴィクターでの第2回目の録音と3回目の録音の間に重要な出来事があった。5月25日に”レッツ・ダンス”の放送が終了したのである。ナビスコはこのヒット番組を何故か早まって終わらせてしまったとグッド氏は述べているが、ともかく放送は終了した。
グッド氏は、番組の終わりころ、BGは出来るだけ聴衆にアピールするようにコマーシャルなサウンド作りを考えていたそうだが、ジョン・ハモンド氏はスイングに重点を置くべきだと穏やかに助言し、プレイヤーやアレンジャーをスカウトして、よりクリエイティヴなサウンドを目指すようBGに決意させたと書いている。現在で考えれば、「聴衆にアピールするようにコマーシャルなサウンド」が「スイング」ではないかという気がしますが、当時はヴァイオリンなどを入れたスイートな音楽が聴衆にアピールするとBGは考えていたのだろう。
一方プレイヤーたちは音楽的な興奮を楽しんでいたともグッド氏は書いている。しかし「レッツ・ダンス」でのBGのバンドはまだ定着していたとは言えなかったようで、ピー・ウィー・アーウィン(Tp)の証言によれば、ピー・ウィー、ジョージ・ヴァン・エプス(Gt)とトゥーツ・モンデロ(As)は同時期レイ・ノーブルのバンドでもプレイしていたという。そしてそれは特別なことではなかった。というのもまだBGの仕事はまだステディなものではなかったからだという。
 BGにとってとても幸運なことは、非常に熱心な救援者が二人いたことである。一人はこれまでも何度か登場した大金持ちのお坊ちゃんで音楽ビジネスでも頭角を現しつつあったジョン・ハモンド(写真右)、もう一人は今回初登場のウィラード・アレクサンダーという人物である。このウィラードについてグッド氏と油井正一氏では記述が異なる。
BGにとってとても幸運なことは、非常に熱心な救援者が二人いたことである。一人はこれまでも何度か登場した大金持ちのお坊ちゃんで音楽ビジネスでも頭角を現しつつあったジョン・ハモンド(写真右)、もう一人は今回初登場のウィラード・アレクサンダーという人物である。このウィラードについてグッド氏と油井正一氏では記述が異なる。
まずグッド氏の弁。「ウィラード・アレクサンダーは、ダンス・バンドのブッキング・オフィスの最大手MCAの駆け出しエージェントだった。彼はBGのバンドが気に入り契約を結んだ。彼はBGがカサ・ロマ・オーケストラに比肩する大成功を収められると信じていた。」
一方油井氏の弁。「ペンシルヴァニア大学在学中から、バンド・マネージメントの才腕を買われていたウィラード・アレクサンダー。」
少し前のこととなるが、このウィラードとBGのエピソードを紹介しておこう。
ウィラードは、BGのバンドに対して1934年末頃から35年にかけてのことだが、ワンナイト興行の話を持ってきた。それはペンシルヴァニア州のジョージ・F・パヴィリオンでの仕事で、このパヴィリオンは全米きっての大ボールルームの一つだった(現在と言っても1987年では「ザ・ファウンテンズ・パヴィリオン」として残っていた)。
BGはサイドマンとして週300ドル稼いでいた。ウィラードは契約を交わしてからBGに報酬の話をした−350ドル+歩合、BGはそれを聴いてまぁ、良かろう、妥当な線だ、でバンドはいくらもらえるんだね?
ウィラード「350ドルというのは、君とバンドの分だ」
BGは金切り声を上げたという。が、結局BGはその仕事を受けた。かなり強引な手腕ぶりがうかがえるが、まだまだ不景気の中そのくらいの剛腕でなくてはこの世界ではやっていけないということであろう。

<Date&Place> … 1935年6月25日 ニューヨークにて録音
前回1935年4月19日からの移動
Trumpet … ピー・ウィー・アーウィン ⇒ バニー・ベリガンBunny Berigan
Trombone … ジャック・ティーガーデン ⇒ ジャック・レイシーJack Lacey
Guitar … アラン・リュース ⇒ ジョージ・ヴァン・エブスGeorge van Eps
<Contents> … 「コンプリート・ベニー・グッドマン」(BMG BVCJ-7030)
| CD1-11. | ゲット・リズム・イン・ユア・フィート | Get rhythm in your feet ( and music in your soul) |
| CD1-12. | バラード・イン・ブルー | Ballad in blue |
| CD1-13. | ブルー・スカイズ | Blue skies |
| CD1-14. | ディア・オールド・サウスランド | Dear old southland |

注目はTpのベリガンであろう。またこの日のアレンジは、フレッチャーがCD1-11,13、弟ホレスがCD-14、弟子のスパッドがCD1-12と分担して担当。野口氏は「バンドに一段と張りが出て好調としている。
CD1-11.[ゲット・リズム・イン・ユア・フィート]
どこかで聞いたことのあるメロディのスインギーなナンバー。ウォードのヴォーカルが入る。ソロはBGのCl、ものすごく短いベリガンのTpくらいで、アンサンブルが中心である。
CD1-12.[バラード・イン・ブルー]
タイトルの通りのバラード。BGのClソロは入るが、アンサンブル中心で、柔らかなアンサンブルが心地よい。インスト・ナンバー。
CD1-13.[ブルー・スカイズ]
こちらも小気味よくスイングするアンサンブル中心のナンバー。ソロはBGのクラリネットくらいである。
CD1-14.[ディア・オールド・サウスランド]
これもアンサンブル中心のインスト・ナンバーでベリガンのソロは聴こえない。

<Date&Place> … 1935年7月1日 ニューヨークにて録音
<Personnel> … ベニー・グッドマン・アンド・ヒズ・オーケストラ(Benny Goodman and his orchestra)
前回1935年6月25日からの移動
Trumpet … ジェリー・二アリー ⇒ ラルフ・ムジロRalph Muzzillo
<Contents> … 「コンプリート・ベニー・グッドマン」(BMG BVCJ-7030)&“Giants of Jazz/Benny Goodman”(Time-Life)
| CD1-15. | サムタイムズ・アイム・ハッピー | Sometimes I’m happy |
| CD1-16、record1 B-4. | キング・ポーター・ストンプ | King porter stomp |
| CD1-17. | 絶体絶命 | The devil and the deep blue sea |
| CD1-18. | ジングル・ベル | Jingle bells |
約2週間後の7月1日の吹込みでメンバーはそれほど移動はない。野口久光氏は、「BGは最高のプレイで我々を圧倒する」と述べている。
CD1-15.[サムタイムズ・アイム・ハッピー]
ミュージカル「ヒット・ザ・デック(Hit the deck)」(1927)の主題歌。フレッチャー・ヘンダーソンのアレンジを十分生かした上にBG、ベリガンのソロによって第一級のビッグ・バンド・ジャズに仕上げているというが、アンサンブルも見事である。
CD1-16、record1 B-4..[キング・ポーター・ストンプ]
ジェリー・ロール・モートンの傑作曲をフレッチャーがアレンジしたもの。ヘンダーソン・バンドとは一味違った明朗で力強い演奏で、BGバンドのベストに上げたいくらいだとは野口氏。確かに最後のリフの部分など聴き応え十分で、前曲とこの曲が水準を超えた素晴らしい演奏であることはよく分かる。ベリガンのソロもよく歌っている。
CD1-17.[絶体絶命]
ウォードのヴォーカル入り。ハロルド・アーレンの曲で拙HPでは初演キャブ・キャロウェイやルイ・アームストロングのナンバーなどを取り上げてきた。
CD1-18.[ジングル・ベル]
超、超有名なクリスマス・ソング。当時からクリスマス・ソングだったのだろうか?野口氏も何もコメントしていないが、この時代からある曲なんだなぁと感じ入ってしまう。ベリガンの他Tsソロもいい。
さて、BGを中心に録音履歴を見ると、次の録音はテディ・ウィルソンのコロンビア系ブランズウィックへの録音に見返り参加したものになる。テディ・ウィルソンは、会社が望むものは何でも録音するという条件で週に100ドルを保証され、ブランズウィックと契約していた。ジョン・ハモンドはブランズウィックの重役たちに、テディがBGと一緒にヴィクター・レーベルに吹き込む許可が得られるように頼み込んだ。その条件として彼は将来BGがテディのブランズウィック・セッションに加わることを申し出た。ブランズウィックの社長ディック・アルトシュラーはその要請を承認し、BGは7月2日にテディのオーケストラのサイドマンとして録音に参加することになった。
というが先般とは話が異なる。テディ・ウィルソンのビリー・ホリディを歌手に立てた吹込みへの参加は、通常御法度の他社に吹き込んだばかりの曲を直ぐ追っかけで録音するのを許可する代わりに、ブランズウィック専属だったテディ・ウィルソンの吹込みにBGがサイドマンとして参加するという条件で吹込みがOKになったはずである。多分ジョン・ハモンドは、これから後もBGバンドへのウィルソンの参加、見返りとしてBGもウィルソンの吹込みへ参加するということを交渉したのであろう。
さてこの録音は、現在どのレコードで入手可能であるか?この録音は写真左ビリー・ホリディのレコードで聴くことができる。

<Date&Place> … 1935年7月2日 ニューヨークにて録音
<Personnel> … テディ・ウィルソン・アンド・ヒズ・オーケストラ(Teddy Wilson and his Orchestra)
豪華な顔ぶれである。初登場はロイ・エルドリッジとコジー・コール。スイング時代最高のトランペット奏者と言われるロイ・エルドリッジの多分初レコーディングである。エルドリッジのディスコグラフィーでは、初録音は1936年2月5日自己名義のレコードとなっているが、それよりも半年早い。コジー・コールは、1930年ジェリー・ロール・モートンとのレコーディングがデビューだったようだが、そのレコードは持っていない。拙HPでは初である。
<Contents> … 「ビリー・ホリディ物語」(CBS SONY SOPH 61-62)
| record1-3. | 月に願いを | I wish on the moon |
| record1-4. | 月光のいたずら | What a little moonlight can do |
| record1-5. | ミス・ブラウンを貴方に | Miss Brown to you |
| record1-6. | 青のボンネット | A sunbonnet blue |
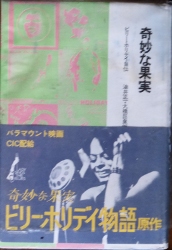
「ビリー・ホリディ物語」解説の大和昭氏は、「リズム隊の躍動感は見事であり、生き生きとした雰囲気に満ちている。エルドリッジの鋭さ、ウエブスターの豪快さ、グッドマンの軽妙さとフロント・ラインの3人が三者三様の素晴らしい出来を示している」と書いているが、確かにこれぞスイング時代最高のコンボ演奏の一つと言えると思う。
record1-3.[月に願いを]
もう一人の解説者、大橋巨泉氏は、初録音から2年がたち、ビリーもグッと落ち着きを見せるとし、グッドマンも未完成だが、トーンに色気があり、歌のバックもいい、この二人は恋仲だったかもしれないと書いている。確かに恋仲だったのであろう。それはビリー自身が自伝『奇妙な果実』(油井正一、大橋巨泉訳 晶文社)で明らかにしていることである。またラスト16小節をリードするエルドリッジは抜群である。
record1-4.[月光のいたずら]
軽快なテディのイントロに乗って出るBGのソロがいい。前半は中・低音を使い、後半は高音部でぐいぐいとスイングする。大和氏、巨泉氏ともBG最高のソロの一つとしているが確かに素晴らしい。この後のビリーの歌唱もまた素晴らしく、それにつられてかウエブスターも素晴らしい吹奏ぶりをしめす。
原曲の譜面を確認した巨泉氏は、全くつまらない流行歌をここまで名作に仕立て上げたのはこの面子だからであると述べている。
record1-5.[ミス・ブラウンを貴方に]
この曲でBGはイントロは高音で、メロディは中・低音でと展開を変えており、彼の好調ぶりを示している。ビリーとウエブスターが、レスターとのように溶け合っていないが、ウィルソン、エルドリッジが良くコールのブラシでのドラミングも素晴らしい。
record1-6.[青のボンネット]
この曲録音前になぜかBGは帰ってしまい、参加していないという。ウエブスター、エルドリッジの出来が素晴らしい。
余談
 僕はどうしても気になることがある。以下は右ビリー・ホリディの自伝『奇妙な果実』(油井正一、大橋巨泉訳 晶文社)の次のくだりである。1973年に刊行された初版十刷ではP68〜69にかけての記述である。
僕はどうしても気になることがある。以下は右ビリー・ホリディの自伝『奇妙な果実』(油井正一、大橋巨泉訳 晶文社)の次のくだりである。1973年に刊行された初版十刷ではP68〜69にかけての記述である。
いつのころのことかは明確な記述はないが、
「毎朝仕事が終わってから、きっとどこかで大きなジャム・セッションがあった。ベニー・グッドマンやハリー・ジェイムスのようなミュージシャンもラジオの仕事が終わってからよく現れた。そして優秀な黒人、ロイ・エルドリッジ、レスター・ヤング、ベン・ウエブスターなどと一緒にジャムを楽しんだ。みんなが私の友達だったが、ベニー・グッドマンとの交際は特別の関係である。
私と彼は1週間に一度は、きっとこういうジャム・セッションの席で落ち合い、数時間を一緒に過ごしたが、ママはこの点では特に私に厳格で、白人の青年と一緒に歩き回ってはいけないと、くどいほど私に注意を与えた。
ベニーの姉のエセルは当時、彼のマネージャーをやっていた。彼女は、ベニーがきっとバンド・リーダーとして大物になるに違いないと目安を付けていたので、弟が黒い女と問題を起こして出世を棒に振ることを望まなかった。
ベニーは立派な男だった。絶対に退屈な男ではなかった。二人は一緒に過ごすために、ママや姉の裏をかいた。ベニーとの交際は私が別の恋愛に悩むようになるまで、相当長い間続いた。」
この後その別の恋愛のことに話題は移るのだが、ビリー曰く「二人は<いい仲>で、それは相当長い間続いた」と。しかしこのことについて触れた記述を他に見たことがない。
ベニー側の考えは姉の言う通り、「黒人女と問題を起こして出世を棒に振りたくない」という一点に尽きるであろう。そしてビリー側は、このことをあげつらって白人ジャズの王様、ベニー・グッドマン或いはその側近、さらに利害を共にするレコード会社などの連中に潰されたくないということでダンマリを決め込んだのだろうか?それとも単なるビリーの妄想であったのであろうか?
確かにこれは単なる男女のスキャンダルで音楽には関係ないという意見もあるかもしれない。それなら著名なジャズ評論家レナード・フェザー氏が、「彼(BG)は、意味深いことに、アリス(ジョン・ハモンド氏の妹)の誠実な夫であり、二人の娘たちの愛情深い父親であり、かつアリスが前の結婚でもうけた三人の子供たちの献身的な養父でもあった」というのも意味をなさないこととなる。
僕は、ビル・クロウがその著『さよなら、バードランド』に書くようにBGは自分のイメージ管理に最も腐心した男であったような気がする。最近で言われる『好感度』重視である。「良き夫であり、良き父親」であるというイメージがこの後彼の成功に大いに貢献したのではないかと思うのである。成功したミュージシャンが数多くの発表の機会を持ち、録音の機会を持つのは当然である。そして一面そうやってジャズの歴史は作られていったのである。

アメリカの夏はいつ始まるのでしょうか?
「レッツ・ダンス」のラジオ放送が終了後、BGは仕事を探していたといいます。この頃はまだ、BGのバンドは安定していたとは言えない状況だったことは、メンバーでTp奏者のピー・ウィー・アーウィンが証言しています。つまり次々と仕事を入れて稼がないとバンドの維持は難しくなったのでしょう。
そこでMCAのマネージャー、ウィラード・アレクサンダーは、MCAのボス、ビリー・グッドハートとソニー・ウェーブリンに、BGのバンドとルーズヴェルト・ホテル・グリルとの契約について話をしました。そのグリルは落ち着いた店で、いつもはスイート・ミュージックのガイ・ロンバードのバンドが出演していました。もしロンバード楽団がツアーに出ている場合には、バーニー・カミンズのバンドが代役でしたが、これもコマーシャルなスイート・バンドでした。ガイ・ロンバードのバンドが1935年の夏季の不在期間、ウィラードの熱意により、ルーズヴェルト・グリルとの出演契約が締結されたとグッド氏は書いています。一方油井正一氏は、ウィラードとハモンド二人の肝入りで、ニューヨークのホテル・ルーズヴェルト出演が決まったと書いています。
しかしこの時期油井氏は、BGは本当に自信を失っていたと記しています。「ドア・ボーイまでが、このろくでなしのミュージシャンと僕の顔を眺めていたんだ」と言っていたそうです。
ということは、BGのバンドはレコーディングは順調でしたが、バンド自体はうまく行っていなかったのでしょうか?これは僕の推測ですが、当時レコーディングはそれほど実入りの良い仕事ではなかったのではないでしょうか?印税が得られる契約だったことは前に書きましたが、儲かるのはレコードが売れた場合で、売れなかったらそれに伴って収入は減るはずです。「パロマ―」での大成功によって、売れ残っていた大量のBGのレコードが大量に売れ、ファンが探し回る事態になったことは後の話です。
さて、このルーズヴェルト・ホテル・グリルへの出演の出来事について、グッド氏は次のように書いています。
「ルーズヴェルト・グリルはさほど広くない店で、ガラスのパネルが部屋を包み、同じ高さで掲げられている。バンド・スタンドは、ロンバードやカミンズのように少人数のバンドにはピッタリだが、BGのバンドのサウンドには不向きだった。クルーパの大きなドラム・セットを入れるだけでスタンドはいっぱいになってしまった。バンドの音はそれまでのソフトなムードを一変した。ガラスのパネルはビりついた。」さらにAs奏者のハイミー・シャーツアーは、その夜のことを思い出して次のように語っています。
「そりゃもう恐ろしいもんだった。ヘッドウェイターはこう喚いた。デカ過ぎるよ!デカすぎる。」
ホテルの社長ハインズ氏は最初の演奏を聴き逃し、2回目の演奏の丁度強烈な個所に差し掛かったところに姿を現しました。そしてウィラードとBGのバンドに向かって、聴いている全員に向かって、騒音取締令を読み上げました。ハインズ氏は激怒を込めてこう締めくくった。「全員クビだ!たった今だ!」
しかしその夜そこに居合わせた人達の中には、少し違った感じ方をした人もいました。例えばジョージ・サイモン氏で彼は『メトロノーム』誌にこのバンドの批評を次のように書いています。
「メンバー全員一体となったビッグ・サウンド、最高のアレンジと驚くべきアンサンブル、強烈なスイング感は驚嘆に値するが、この場所は必ずしも適切とは言えない。それでもベニーと楽団は巧みにプロの面目を保って落ち着いたタイプのスイング・ミュージックを演奏し、それはグリルのいたあらゆる年齢層の人々を引き付けた。すべて趣味の良いものだった」と。

<Date&Place> … 1935年7月13日 ニューヨークにて録音
<Personnel> … ベニー・グッドマン・トリオ(Benny Goodman Trio)
<Contents> … 「コンプリート・ベニー・グッドマン」(BMG BVCJ-7030)&“Giants of Jazz/Benny Goodman”(Time-Life)
| CD1-19、record1 B-5. | 君去りし後 | After you’ve gone |
| CD1-20、record1 B-6. | 身も心も | Body and soul |
| CD1-21. | フー | Who |
| CD2-1. | サムディ・スィートハート | Someday sweetheart |
いろいろと調べてはみたが、現段階で僕はこの録音がホテル・ルーズヴェルト・グリルの後か先かが分かっていない。今後判明したら追記しよう。
さて、この7月13日の初のトリオ・セッションは内容の素晴らしさもさることながら、歴史的にも非常に重要なものとされる。野口久光氏の解説によれば、それは「白人ミュージシャンと黒人ミュージシャンとの共演は、レコードの上では度々行われていて別に問題にはならなかったが、同じステージで共演することは黒人差別意識を持った白人の妨害を恐れて一種タブーのようになっていたのだという。しかしBGは黒人ピアニスト、テディ・ウィルソンを自分のグループの一員にしたいと思い、まずレコードの上でその共演を果たしたのだった。それが即ちBG、ウィルソン、ジーン・クルーパのトリオによる初吹込みとなったこの4曲である」という。
 そして、この見返りにテディ・ウィルソンのブランズウィックへの吹込みにBGがサイドマンとして参加することになる。
そして、この見返りにテディ・ウィルソンのブランズウィックへの吹込みにBGがサイドマンとして参加することになる。
このトリオの誕生は、BGがニューヨークのフォレスト・ヒルズにあるレッド・ノーヴォとミルドレッド・ベイリーの邸で行われたパーティーで座興的に共演してすっかり惚れ込んだのだという。その時はたまたま居合わせたミルドレッドの甥がドラムを叩いたのだが、それでは不十分なのでバンドのドラマージーン・クルーパを加えてトリオにすることにしたのだという。
さらに野口氏は、「この吹込みは簡単な打ちあわせとキーの取り決めだけで演奏したジャム・セッションともいえるものだったが、最上級のインプロヴァイザー三者によるテクニック、精神性(ジャズ・スピリット)を一丸としたプレイには、ジャム・セッションにありがちなルーズさもなく、完璧な構成美をも発揮している。
このBGトリオ以前に、これだけ質の高いコンボ演奏は少なくともレコードには見られなかった。黒人ピアニスト、テディ・ウィルソンには、珍しく黒人的な一種の訛りがなく、ソフィスティケイトされた彼のピアノは、BGのクラリネットに見事にフィットしている。このトリオの発想は勿論BGのものであり、彼はクラリネットにリーダーとしての貫禄を見せているが、ウィルソン、クルーパを同等同格にプレイさせていることも見逃せない」と述べている。
確かにこのトリオ演奏は重要なものという評価が定着しているようで、以前取り上げたTime-Life社で出している”Giants of jazz”シリーズのベニー・グッドマンのボックスは、レコード会社を跨いでいるので1927年から1946年まで膨大な吹込みがある中から40曲が取り上げられているが、1935年のこのトリオの演奏が2曲(「君去りし後」と「身も心も」)も選ばれている。
今の感覚で聴くと特段目新しいところのないトリオ演奏のように聴こえるが、これまでレコードを年代順に聴いてきた耳からするとかなり斬新な演奏である。つまりこの演奏が次世代のスタンダードになって行ったということが言えると思う。4曲ともそれぞれ聴かせ処のある素晴らしい演奏である。テディ・ウィルソンは、ピアノについてはつい最近までストライド奏法かハインズ系かなどという話とは程遠く一人モダンにまで通用するようなスイング・スタイルである。この人はどこでこういうスタイルを身に着けたのだろうか?BGも負けじとジャズ魂を込めて吹き上げる。クルーパはバックに廻っている時の奏しているのは「ブラシ」ではないだろうか?この時代ブラシ・プレイというのは聴いたことがない。誰かドラム奏法におけるブラシ・プレイの歴史を書いてくれないかなぁ。
CD1-19.[君去りし後]
BGは最初からエモーショナルなプレイを展開する。続くテディの短いが端正なソロは聴き応えがある。
CD1-20.[身も心も]
現在もよく歌われ演奏されるスタンダード・ナンバー。初めにテディがソロを取り、続くBGはストレートにメロディを吹く。再びテディのソロとなり、後はBGとテディが短いソロを取り合う。
CD1-21.[フー]
BGとテディのソロの合間にクルーパが見事なブラシによるドラム・ソロを披露する。この時代ブラシによるソロは珍しいのではないだろうか?
CD2-1.[サムディ・スィートハート]
ミディアム・アップのスインギーなナンバー。端正なテディのピアノが良く歌っており、BGのクラリネットよくマッチして上品なスイングを作り上げている。クルーパは途中からスティックでたたいている。
さてここからは、BGがスターダムにのし上がる1935年ロス・アンゼルスのツアーの話題です。このエピソードはよく知られたものですが、油井正一氏が記述するものとCDボックス解説のモート・グッド氏の書くものとは若干内容に食い違いがあります。
 先ず油井正一氏から
先ず油井正一氏から
ホテル・ルーズヴェルトの契約が終わりに近づくと、マネージャーのウィラード・アレクサンダーは、ニューヨークから始まってロス・アンゼルスのパロマ―で終わる一大コンサート・ツアーの計画を押し付けてきました。
この頃、BGは団員の給料、経営上のごたごたに辟易し、一兵卒ならクラリネットを吹くだけで週に300〜500ドルは楽に取れるのにな、と考えると、熱心に後押しをしてくれる二人の支持者(ハモンド氏とアレクサンダー氏)が、後援者どころか自分を苦しめる妖魔の化身にさえ見えたといいます。
「ワシはもう降りる。バンマスはもうこりごりだ。」とひどく落ち込んだBGをハモンドとアレクサンダーはなだめすかし、脅かし、おだて、さんざんかき口説いて渋々承諾させましたが、デンヴァーでは初日が終わるとボールルームのマネージャーから、早くも契約破棄を通告される始末、BGのノイローゼも極限に達し、いよいよお手上げの決意を固めたものの、二人の後援者に「ロスまであと一息」と声援されると、これまでの行為をすっぽかすわけにもいかず、とうとうロスのパロマ―までたどり着いたのです。
ところが人間の運なんてものは分からないもので、別にロスについてからバンド・スタイルを変えたわけでもなく、さんざんののしられ、あざ笑われてきたニュースタイルのダンス音楽をそのまま心細げにやっただけなのに何ということでしょう。
「パロマ―にデビューしたBGのダンス音楽−俄然、市民の絶賛を浴びる」というニュースがアメリカ中に伝わり、レコード屋でホコリにまみれていた彼のレコードは、羽が映えたように売れ出したのです。カリフォルニアこそジャズを正当に受け入れてくれる要素に満ちていたのです。
BGがロス・アンゼルスまで尻をひっぱたかれながらたどり着いたことこそ、幸運の始まりだったのです。ハリウッド放送局のアル・ジャーヴィス(ディスク・ジョッキーの草分け)が、毎日のようにBGのレコードをかけ、ファンを作っていてくれたこと、それに不況から立ち直って人心が安定してきたことが何よりの背景となりました。
これに続いてシカゴのコングレス・ホテルとの契約、そしてニューヨークのペンシルヴァニア・ホテルへ…。NBCネットワークを通じて流れ出るBGの音楽は、実にジャズが何らの懸念なしに、全米の善良な家庭のスピーカーを通じて流れ出した最初の出来事になりました。
続いてグッド氏
 7月13日のトリオ録音直後からバンドは長いツアーに出、ロサンゼルスのパロマ―における3週間にわたる公演のため、西海岸に向かった。このツアーの間にミシガン州ジャクソンの「オーシャン・ビーチ・パイアー」、オハイオ州コロンブスの「オレンタジー・パーク」、ミシガン州レイクサイドの「ルナ・パーク」、ウィスコンシン州ミルウォーキーの「モダニスティック・ボールルーム」、コロラド州デンヴァーの「エリッチズ・ガーデンズ」(3週間 前回写真を掲載)、コロラドのグランド・ジャンクション、カリフォルニア州のピスモ・ビーチといったといったダンス・スポットに出演した。
7月13日のトリオ録音直後からバンドは長いツアーに出、ロサンゼルスのパロマ―における3週間にわたる公演のため、西海岸に向かった。このツアーの間にミシガン州ジャクソンの「オーシャン・ビーチ・パイアー」、オハイオ州コロンブスの「オレンタジー・パーク」、ミシガン州レイクサイドの「ルナ・パーク」、ウィスコンシン州ミルウォーキーの「モダニスティック・ボールルーム」、コロラド州デンヴァーの「エリッチズ・ガーデンズ」(3週間 前回写真を掲載)、コロラドのグランド・ジャンクション、カリフォルニア州のピスモ・ビーチといったといったダンス・スポットに出演した。
BGはウェスト・コーストのツアーに際し、何人かのメンバー移動を考えていた。ルーズヴェルトでの災難以来、レコーディングを除いてはさほど大きなメンバー・チェンジは無かった。ハイミーはその時のことを思い出して語る。
「BGはピッツバーグから何人かのメンバーを選び出した。ビル・デピュはアルトを吹き、バンドのサウンドを補完した。ジェス・ステイシーも入ってきた。それにトロンボーンのジャック・レイシーもだ。この連中は、BGのバンドでやりたい一心で現地のラジオの仕事を放り出しても全然気にしなかった。」
トゥーツがツアーに参加しなかったのは、ニューヨークに留まっていたからである。トゥーツがこの町を愛しているのは現在(1987年以前)でも変わりない。彼は当時ショウ・ビジネス会の人間やミュージシャンたちの溜まり場だった、ホイットビー・アパートメントに住んでいた。BGもそこに住んでいたことがあり、グレン・ミラーやジーン・クルーパ、その他にも大勢いた。トゥーツは今なおそこに住んでいる。
トゥーツや他のメンバーは、BGからツアーを強制されたわけではなく、バンド自体もハッキリと確立されたものではなかった。ニューヨークにはラジオやスタジオの仕事がいくらもあった。そしてトゥーツとジョージ・ヴァン・エプスとピー・ウィー・アーウィンは組んでレインボウ・グリルのレイ・ノーブル楽団で働いていた。シャーツアーは次のように回想する。
「ルーズヴェルトの一件があり、仕事を失くしたからと言って、デンヴァーのエリッチズ・ガーデンズに着くまでは、バンドを根底から揺さぶるようなことは何もなかった。だけど、あの時は本当にひどいものだった。客の入りは良くなかったが、我々はいつも“レッツ・ダンス”の時のアレンジ譜や録音の時のアレンジで演奏していたから、旅は楽しかった。ある程度成功も収めたしね。
ところがエリッチズでは、客が全然入ってこないんだ。ひと握異の連中がダンスをしていると、オーナーが飛んで来て言った。『ヘイ、あんた、アレンジが長すぎるんだよ。1分を超えないようにカットしてくれ―ここのダンスは一踊り幾らのダンスのスタイルなんだから』そういう類の店だったのさ。彼はホステスを抱えていて、音楽が途切れないよう望んでいた。全く参ったよ。仕方なく私たちはアレンジを変え始めた。私たちは2、3週間そこに留まりその後ワンナイト・スタンドでオークランドに行ったのだった。
 (写真右はツアー中の右からBG、ヘレン・ウォード、レッド・バラード、バラードの妻アジ― )
(写真右はツアー中の右からBG、ヘレン・ウォード、レッド・バラード、バラードの妻アジ― )
私たちが到着すると、ボールルームはぎっしり人が詰まっていた。何百人もの人が私たちの前に立っている。それというのもウエスト・コーストでは、彼らが私たちのレコードを持っていたからで、ディスク・ジョッキーの一人、アル・ジャーヴィスだったと思うが、彼が私たちのレコードを定期的にかけてくれていたからだった。彼らは私たちのアレンジをよく知っていて、バンドを愛してくれた。」
翌日バンドはこの幸せな気分で「パロマー・ボールルーム」に出演。それは8月21日のことで、この日がスイング時代の幕開けとされている。
バンドはその日の演奏を、何曲かの比較的静かな曲で開始した。最初のセットでは、熱狂的な反響を得られなかった。BGは、メンバーの旅の疲れを思いやって調子を落とした演奏をやらせていた。その内にジーン・クルーパがたまりかねBGに言った。
「もし俺たちが死にかけてるんなら、俺たち自身の演奏をしながら死のうじゃないか」
BGはそれに同意して次のセットではヘンダーソンと他のスインギーなアレンジを使うことに決めた。BGがその反応を書き記している。
「ベリガンが立ち上がり、“サムタイムズ・アイム・ハッピー”と“キング・ポーター・スイング”を吹いた時、場内は爆発した。
 そのニュースは大陸を横切り、ニューヨークのMCAのオフィスに届いた。当時ウエスト・コースト・オフィスのバンド契約担当者だったタフト・シュライバーは、翌朝ニューヨークに電話を入れた。今では自信を失いかけていたバンドの擁護者ウィラードは、それまで行く先々で聴衆の不評に気を落としていた。その時彼はビリー・グッドハートのオフィスに呼び出され、ソニー・ウェーブリンと3人のエージェントたちは、ロスからの電話の声に耳を傾け、それぞれ自分の耳を疑った。タフトがバンドのウエスト・コーストでの大成功を知らせてきたのだ。
そのニュースは大陸を横切り、ニューヨークのMCAのオフィスに届いた。当時ウエスト・コースト・オフィスのバンド契約担当者だったタフト・シュライバーは、翌朝ニューヨークに電話を入れた。今では自信を失いかけていたバンドの擁護者ウィラードは、それまで行く先々で聴衆の不評に気を落としていた。その時彼はビリー・グッドハートのオフィスに呼び出され、ソニー・ウェーブリンと3人のエージェントたちは、ロスからの電話の声に耳を傾け、それぞれ自分の耳を疑った。タフトがバンドのウエスト・コーストでの大成功を知らせてきたのだ。
ハイミーはこう言う。
「とても信じられなかった。何百人もの人間がバンドの前に立っていた。彼らはアレンジを知っていたし、それを好んでいた。それにもう一つ不思議なことにい、私たちがバンドを呼び出すのに演奏した曲は、“レッツ・ダンス”ショウからのいつものテーマ曲じゃなかったんだ。BGはオープニングとして、呼び出し用テーマに“グッドバイ”を使い、しかもそれはつぎはぎだらけのアレンジだった。約6分間も続いたんだが。」
スイング・イーラが活動を開始した―ウエスト・コーストで。だがBGバンドの成功は、まだローカルなものだった。「パロマ―」では、ハリウッドのファンに爆発的に受けはしたが、まだ全国的な人気とは言えなかった。
1935年8月21日の「パロマ―の爆発」の後の最初のレコーディングは9月27日に行われた。グッド氏の解説に拠れば、パロマ―での契約終了後、バンドはシカゴのシカゴのコングレス・ホテル内の「アーバン・ルーム」の仕事に入ったが、その時はバニー・ベリガンは故郷に帰るためにバンドを離れていたとある。9月27日の録音にはベリガンの名前が見えることから推測すると、シカゴでの仕事の前に録音は行われたのであろう。そしてこのメンバーは、グッド氏の解説と照合すると長期のツアーをBGに帯同し、パロマ―の爆発を経験したメンバーである。

<Date&Place> … 1935年9月27日 ロスアンゼルス・ハリウッドにて録音
<Personnel> … ベニー・グッドマン・アンド・ヒズ・オーケストラ(Benny Goodman and his orchestra)
前回7月1日からの移動分。
Trombone … ジャック・レイシー ⇒ ジョー・ハリスJoe Harris
Alto sax … トゥーツ・モンデロ ⇒ ビル・ドペゥBill DePew
Piano … フランク・フローバ ⇒ ジェス・ステイシーJess Stacy
Guitar … ジョージ・ヴァン・エブス ⇒ アラン・リュースAllan Reuss
<Contents> … 「コンプリート・ベニー・グッドマン」(BMG BVCJ-7030)
| CD2-2. | サンタが春にやって来た | Santa Claus came in the Spring |
| CD2-3. | グッドバイ | Goodbye |
| CD2-4. | マッドハウス テイク1 | Mad house take1 |
| CD2-5. | マッドハウス テイク2 | Mad house take2 |
楽曲解説の野口久光氏は、この3曲(別テイクあり)について全く触れていない。特に触れる必要もないという判断なのであろう。録音は西海岸ハリウッドで行われている。パロマ―の後他のボールルームなどに出演し9月末まで滞在していた可能性がある。
CD2-2.[サンタが春にやって来た]
ヴォーカル入りで、歌っているのはトロンボーンのジョー・ハリスという。なかなかうまいものだ。パロマでの爆発の後だからかバンドは自信に満ちて堂々としているように聴こえる。
CD2-3.[グッドバイ]
ラジオ・ショウ「レッツ・ダンス」のクロージング・テーマ。ゆったりとしたちょっとセンチメンタルなナンバーで、いかにも別れの寂寥感を感じさせる。
CD2-4,5.[マッドハウス]
新加入のピアニスト、ジェス・ステイシーの初ソロが聴ける。BGのソロも好調である。バンドもよくスイングしている。全体としてブンブンと低音部を支えるハリー・グッドマンと全体を鼓舞するクルーパの役割が効いている。
パロマ―との契約が終了すると、バンドはシカゴのコングレス・ホテル内の「アーバン・ルーム」の仕事に入った。部屋は他のバンドによって汚されており、ホテルもトップ・クラスではなかったという。
そして先ほども触れたように、バニー・ベリガンは故郷のウィスコンシン州フォックス・レイクに帰るためにバンドを去り、ジャック・レイシーはハリウッドで、ジョー・ハリスはバンド・ヴォーカリストの椅子を引き継ぐためにニューヨークで既にバンドを去っていた。
グッド氏は以下のように記す。「どのような魔術だったのか、「アーバン・ルーム」ではそれが一時に起きた。若者たちがやって来た、聴き、踊り、声援を送るために。オーケストラは成功を収め、その音楽の人気は急上昇した。
そしてヴィクターへの1935年最後の録音が11月22日に行われることになるのだが、左のプレスティッジ盤に11月19日吹込みの4曲が収録されている。「あれ?BGはヴィクターの専属ではなかったか」と思ってTime-Lifeのボックスを見るとこの4曲中の1曲が収められており、名義は「ジーン・クルーパと彼のオーケストラ」となっている。Time-Lifeの解説に拠れば、この録音はコングレス・ホテルに出演中にシカゴで行われたものだという。ジョン・ハモンド氏がクルーパ名義の録音をイギリスのパーロフォン(Parlophone)社に残したいと考えて行われたものだという。

<Date&Place> … 1935年11月19日 シカゴにて録音
<Personnel> … ジーン・クルーパ・アンド・ヒズ・オーケストラ(Gene Krupa and his orchestra)
<Contents> … "Benny Goodman and the giants of swing"(Prestige 7644)&“Giants of Jazz/Benny Goodman”(Time-Life)
| A-5. | ザ・ラスト・ラウンドアップ | TheLast roundup |
| A-6. | ジャズ・ミー・ブルース | Jazz me blues |
| B-1、record1 B-7. | スリー・リトル・ワーズ | Three little words |
| B-2. | ブルース・オブ・イスラエル | Blues of Israel |

EMI系のレコード会社パーロフォンに版権があるとすると、中々再発売はしにくいのかもしれない。あまり見かけない録音のような気がするが、実に重要な録音である。まずこの録音は当時のBGのバンドから8名が選ばれる形で行われた。しかし一人だけBGバンドのメンバーではない人物が加わっている。ベースのイスラエル・クロスビーである。黒人で10代でフレッチャー・ヘンダーソンのバンドでデビューし、天才と騒がれた逸材である。当時はブギ・ウギ・ピアニストのアルバートアモンズと仕事をしているところをジョン・ハモンドによって発見され、BGに紹介して起用することになった。この逸話は後のチャーリー・クリスチャンをBGに引き合わせたエピソードと酷似している。ハモンドという人は実にフェアな感覚の持ち主で、天才の肌の色が黒いと何か問題なのか?とでも言わんばかりに素晴らしいタレント・スカウトをしている。
A-5.[ザ・ラスト・ラウンドアップ]
いきなりブギ・ウギの強烈なリズムで始まる。しかしブラス、ホーンが入るとこれまた突然にデキシーランド風の集団演奏になるという不思議な展開を見せる。ソロはケイズビア⇒BG⇒ケイズビア。
A-6.[ジャズ・ミー・ブルース]
こちらは最初からデキシーランド風のスタイルである。なぜこの時期にこのようなスタイルを取って演奏を行ったのだろう?グッド氏が正当な評価を受けていないトランぺッターというように、全般を通して彼の高い能力がうかがわれる吹奏ぶりである。
B-1.[スリー・リトル・ワーズ]
前年1934年デューク・エリントンの演奏が大ヒットとなった曲。これもデキシーランド風に始まる。まずTsのクラーク、続いてステイシーとソロが続き、最初はベースのみ、その後クルーパのドラムをバックにBGが2コーラスのソロを取る。このソロが見事で、クルーパは「BGのレコードで聴かれる最上のソロの一つ」と言っていて、BGもそれを認めているという。
B-2.[ブルース・オブ・イスラエル]
「イスラエル」は国ではなくベーシストの方。タイトル通りイスラエルをフューチャーしたブルース。イスラエルの力強いベース・ソロに始まり、ケイズビアのTpソロ、ステイシーのピアノ・ソロの左手はブギ・ウギ調である。続くハリスのTbソロも素晴らしい。そしてイスラエルのソロで終わる。
全般を通してクルーパとイスラエルの力強いビートにプッシュされ、2人にインスパイアされたBG、そしてこの3人に鼓舞され各人が素晴らしい演奏を展開している。

<Date&Place> … 1935年11月22日 シカゴにて録音
<Personnel> … ベニー・グッドマン・アンド・ヒズ・オーケストラ(Benny Goodman and his orchestra)
11月19日からの移動
Trumpet … バニー・ベリガン ⇒ ハリー・ゲラーHarry Geller
<Contents> … 「コンプリート・ベニー・グッドマン」(BMG BVCJ-7030)
| CD2-6. | サンドマン | Sandman |
| CD2-7. | ヤンキー・ドゥードル・ネヴァー・ウェント・トゥ・タウン | Yankee doodle never went to town |
| CD2-8. | ノー・アザー・ワン | No other one |
| CD2-9. | イーニー・ミーニー・マイニー・モー | Eeny meeny miney mo |
| CD2-10. | ベイズン・ストリート・ブルース | Basin street blues |
| CD2-11. | イフ・アイ・クッド・ビー・ウィズ・ユー | If I could be with you |
| CD2-12. | 仏陀のほほえみ | When Buddha smiles |
クルーパ名義の録音の3日後の11月22日ヴィクターへのこの年最後となる録音が行われる。ヴィクターへの録音なので、ベースのイスラエルがグッドマンに戻り、ベリガンが抜けた後にはハリー・ゲラーが入った他は9月27日と同じメンバーである。
CD2-6.[サンドマン]
ヘンダーソンのアレンジのインスト・ナンバー。安定した典型的なスイング・スタイルによる演奏。BG、Tpソロが入る。
CD2-7.[ヤンキー・ドゥードル・ネヴァー・ウェント・トゥ・タウン]
ヘレン・ウォードのヴォーカル入り。安定したスイング感に満ちている。BGは「ヤンキー・ドゥードル」の一説を引用しながらユーモラスなソロを展開する。
CD2-8.[ノー・アザー・ワン]
ヘレン・ウォードのヴォーカル入り。アレンジはスパッド・マーフィ―。これも実にスインギーに仕上げている。
CD2-9.[イーニー・ミーニー・マイニー・モー]
ヘレン・ウォードのヴォーカル入り。タイトルは子供の言葉遊びのようなもので日本でいえば、「どれにしようかな、神様の言う通り」のようなものだという。
CD2-10.[ベイズン・ストリート・ブルース]
BGは1931年にチャールストン・チェイサーズというバンド名で一度吹き込んでいる。その時はTbとヴォーカルはジャック・ティーガーデンだった。ここでは同じTbのジョー・ハリスがティーガーデンに似せて歌いソロを取っている。出だしの部分など実にそっくりである。
CD2-11.[イフ・アイ・クッド・ビー・ウィズ・ユー]
ヘンダーソンのアレンジのインスト・ナンバー。珍しいアラン・リュースのギター・ソロが聴ける。
CD2-12.[仏陀のほほえみ]
ヘンダーソンのアレンジのスインギーなナンバー。それにしても「仏陀のほほえみ」とは、変わった題名だなぁ。
モード氏は1935年を次のような言葉で締めている。
「12月8日BGとそのバンドは、アメリカにおける初のジャズ・コンサートの一つを開催した。「アーバン・ルーム」は満員で大騒ぎになった。全国的なパブリシティも得た。「タイム」誌は、1ページ全面を使った写真入りの賞賛記事をBGのために割いた。スイング・イーラに突入したのである」と。「アーバン・ルーム」に出演したのは12月8日が最初だったのだろうか?それともずーっと出演していたが爆発したのが、12月8日だったのだろうか?この辺りの詳しい状況よく分からないが、ともかく「スイング時代」に突入したのである。
このWebサイトについてのご意見、ご感想は、メールでお送りください。
お寄せいただいたご意見等は本文にて取り上げさせていただくことがあります。予めご了承ください。
 つまりこの1935年という年はジャズ年表上、ベニー・グッドマンによって一つの時代を画する「スイング・イーラ」、「スイング時代」の幕が開いた年であるということであろう。こうなるとBGの1935年というよりも「僕の作ったジャズの歴史」で取り上げるべき内容と言える。ここは淡々とBGの活動を追っていき、その影響その他については「僕の作ったジャズの歴史」で取り上げよう。
つまりこの1935年という年はジャズ年表上、ベニー・グッドマンによって一つの時代を画する「スイング・イーラ」、「スイング時代」の幕が開いた年であるということであろう。こうなるとBGの1935年というよりも「僕の作ったジャズの歴史」で取り上げるべき内容と言える。ここは淡々とBGの活動を追っていき、その影響その他については「僕の作ったジャズの歴史」で取り上げよう。

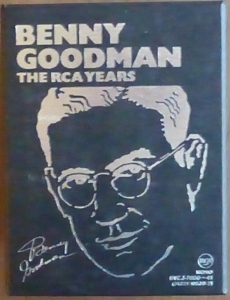 今回からは、ヴィクターに移籍してからの録音を取り上げていこう。
今回からは、ヴィクターに移籍してからの録音を取り上げていこう。 こうしてヴィクター時代に入るのだが、この時代はBGにとってどういう時代かというと、ずいぶん前に紹介した油井正一氏の『生きているジャズ史』のBG―三期説によれば第二期に当たる。
こうしてヴィクター時代に入るのだが、この時代はBGにとってどういう時代かというと、ずいぶん前に紹介した油井正一氏の『生きているジャズ史』のBG―三期説によれば第二期に当たる。




 BGにとってとても幸運なことは、非常に熱心な救援者が二人いたことである。一人はこれまでも何度か登場した大金持ちのお坊ちゃんで音楽ビジネスでも頭角を現しつつあったジョン・ハモンド(写真右)、もう一人は今回初登場のウィラード・アレクサンダーという人物である。このウィラードについてグッド氏と油井正一氏では記述が異なる。
BGにとってとても幸運なことは、非常に熱心な救援者が二人いたことである。一人はこれまでも何度か登場した大金持ちのお坊ちゃんで音楽ビジネスでも頭角を現しつつあったジョン・ハモンド(写真右)、もう一人は今回初登場のウィラード・アレクサンダーという人物である。このウィラードについてグッド氏と油井正一氏では記述が異なる。


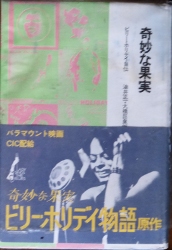
 僕はどうしても気になることがある。以下は右ビリー・ホリディの自伝『奇妙な果実』(油井正一、大橋巨泉訳 晶文社)の次のくだりである。1973年に刊行された初版十刷ではP68〜69にかけての記述である。
僕はどうしても気になることがある。以下は右ビリー・ホリディの自伝『奇妙な果実』(油井正一、大橋巨泉訳 晶文社)の次のくだりである。1973年に刊行された初版十刷ではP68〜69にかけての記述である。

 そして、この見返りにテディ・ウィルソンのブランズウィックへの吹込みにBGがサイドマンとして参加することになる。
そして、この見返りにテディ・ウィルソンのブランズウィックへの吹込みにBGがサイドマンとして参加することになる。 (写真右はツアー中の右からBG、ヘレン・ウォード、レッド・バラード、バラードの妻アジ― )
(写真右はツアー中の右からBG、ヘレン・ウォード、レッド・バラード、バラードの妻アジ― ) そのニュースは大陸を横切り、ニューヨークのMCAのオフィスに届いた。当時ウエスト・コースト・オフィスのバンド契約担当者だったタフト・シュライバーは、翌朝ニューヨークに電話を入れた。今では自信を失いかけていたバンドの擁護者ウィラードは、それまで行く先々で聴衆の不評に気を落としていた。その時彼はビリー・グッドハートのオフィスに呼び出され、ソニー・ウェーブリンと3人のエージェントたちは、ロスからの電話の声に耳を傾け、それぞれ自分の耳を疑った。タフトがバンドのウエスト・コーストでの大成功を知らせてきたのだ。
そのニュースは大陸を横切り、ニューヨークのMCAのオフィスに届いた。当時ウエスト・コースト・オフィスのバンド契約担当者だったタフト・シュライバーは、翌朝ニューヨークに電話を入れた。今では自信を失いかけていたバンドの擁護者ウィラードは、それまで行く先々で聴衆の不評に気を落としていた。その時彼はビリー・グッドハートのオフィスに呼び出され、ソニー・ウェーブリンと3人のエージェントたちは、ロスからの電話の声に耳を傾け、それぞれ自分の耳を疑った。タフトがバンドのウエスト・コーストでの大成功を知らせてきたのだ。

