ビリー・ホリデイ 1935年
Billie Holiday 1935

ビリー・ホリデイの自伝『奇妙な果実』第5章に次のような記述がある。「やがて、私はラジオと映画に出るようになった。(中略)私はポール・ロブソン映画のその他大勢に出してもらい、続いてデューク・エリントンをフューチャーした短編に役を得た。ミュージカルに一寸物語が付いたもので、私は感動的なブルースを歌う機会を得た。しかし役柄は、商売女という一寸苦しいものだった。相手は、あるコメディアンで、彼には悪いが、名を覚えていない。
彼は私のヒモになり、私を殴り倒すことになっていた。
最初の撮影日に、20回も殴り倒された。私はその度、舗道のように塗ってある堅い床の上にひっくり返った。骨の上の肉以外に身を守るものはなかった。
2日目の朝、私がスタジオに現れた時には、もうたおれる気が起こらないほど気が苛立っていた。およそ50回もぶっ倒れたろうか?監督はその度に「カット!」と叫んだ。
私はこの映画をスタジオで1回だけ見た。1回だけで沢山だった。もちろんママは私が大スターになった気で、映画に期待しろと吹聴して歩いた。
一体どこで上映されたか知らないが、つまらない作品で、ミッキー・マウスのフィルムが間に合わない時の埋め合わせにしか過ぎなかった。どこで上映されているか知るためには、私立探偵を雇う必要のある作品だった」と。
 ビリーがどこで上映しているか知るためには私立探偵を雇う必要のあるような短編映画は「シンフォニー・イン・ブラック」("Symphony in black")というタイトルであり、右のデュークのDVDに収録されている。音楽は全篇エリントンが担当しているが、ビリーが出るのは僅かなシーンだけである。念のため映画の内容を簡単に記すと、
ビリーがどこで上映しているか知るためには私立探偵を雇う必要のあるような短編映画は「シンフォニー・イン・ブラック」("Symphony in black")というタイトルであり、右のデュークのDVDに収録されている。音楽は全篇エリントンが担当しているが、ビリーが出るのは僅かなシーンだけである。念のため映画の内容を簡単に記すと、
映画はまずエリントンの事務所に手紙が届くところから映画は始まる。「2週間後に新しい”Symphony of negro mood”黒人の雰囲気の交響曲を完成することになっているのは忘れてないよね」といったちょっとした催促状である。場面が変わってストーリーに入るのだが、エリントンが作曲しながらピアノを弾くと画面がエリントンの楽団の演奏に代わりそれに因んだ映像が流れるという構成で、上記の4つコーナーがある。
黒人労働者
エリントン(ピアノで作曲)⇒白人が観ているコンサート・ホールでのエリントン楽団の演奏⇒黒人が石炭をボイラーに投げ込んだり、麻袋の重そうな荷物を階段で運び上げたりといった重労働で疲れ切った黒人労働者の姿が映し出される。この黒人の労働の場面は”Black and tan fantasy”でも使われた映像のような気がする。ティンパニーを使い重々しい雰囲気の中軽快なアルト・サックス・ソロがちょっと場違いな感じもする。一方の黒人は過酷な労働を強いられ、一方デュークたちは白人社会に向けて、にこやかに黒人の労働者は厳しいんですよと訴えているという構図はいかがなものかと思う。
 恋のトライアングル
恋のトライアングル
全篇にビリーが登場するわけではない。このコーナーは、エリントン(ピアノで作曲)⇒恋人らしき黒人の男女が部屋で踊っている。それを外で窓に映る影を見ている女がビリー・ホリデイである。二人は外出する。そこにビリーが近寄る。会話の音声はないが、ビリーはその男に振られたらしい。「私の所に帰ってきて」と縋りつくような感じである。これを男が突き放し押し倒して、踊っていた女と去って行ってしまう。ビリーは「殴り倒された」というが実際の映像を見ると殴ってはおらず押し倒されたという感じである。そこでビリーが(感動的な)ブルースを歌うのである。
クラリネットの独奏で始まり、短いアンサンブルの後ビリーの歌に入るがちょっと拍数が取りにくい。多分4か5小節、その後ナントンのワウワウ・トロンボーン、そしてビリーのヴォーカルが1コーラス12小節、短いアンサンブルがあり、多分ホッジスと思われるアルトのリードで曲が終わる。
 ビリーのヴォーカルは相当崩しているので拍が把握しづらいがそこがうまさなのだろう、ビリーのアンニュイな歌い方が実に自然に聞こえる。また非常に抑えた表現で素晴らしい。確かに「感動的なブルース」と思う。短いが僕が今のところ最も気に入ったビリーのヴォーカルである。もっと歌って欲しかったな。
ビリーのヴォーカルは相当崩しているので拍が把握しづらいがそこがうまさなのだろう、ビリーのアンニュイな歌い方が実に自然に聞こえる。また非常に抑えた表現で素晴らしい。確かに「感動的なブルース」と思う。短いが僕が今のところ最も気に入ったビリーのヴォーカルである。もっと歌って欲しかったな。
これは記憶だけで違っていたら申し訳ないが、メロディーを崩して歌うあるいは吹奏することは、ビリーがレスター・ヤングから学んだ風に言われることが多いが、実はレスターがビリーから学んだという面が強いということを確か油井正一氏が書かれていたように思う。そしてこういう崩して自分のリズムが乱れないのはルイ・アームストロングとビリーだけだともいう。
悲しみの讃美歌
エリントン楽団の演奏⇒教会で黒人牧師の下で黒人たちが祈りをささげる。柔らかなアンサンブルで安らぎを感じる。
ハーレム・リズム>
エリントン楽団の演奏⇒高級そうなクラブで酒を飲む男女と黒人レビュー、男性のダンサーのステップなどがオーヴァー・ラップで映し出される。当時として最新の技術かもしれない。演奏はリフを取り入れたスインギーな演奏である。
<Date & Place> … 1935年3月12日 ニューヨーク・パラマウント映画スタジオにて録音
![[Billie Holiday/Live and private recordings in Chronological order]ボックス](BillieHoliday_Chronologicalorder_2.jpg)
Ellingtoniaでは1934年10月初旬の録音。
<Personnel ビリー・ホリデイレコード記載> … デューク・エリントン・アンド・ヒズ・オーケストラ(Duke Ellington and his orchestra)
 Ellingtoniaでは、Saxes & Clarinetがマーシャル・ロイヤル(Marshall Royal)ではなく、オットー・ハードウィックとなっているだけで他は一致する。しかし上記パーソネルではアーサー・ウェッツェル、フレディ・ジェンキンスも在団していることになり、またベースも。ウェルマン・ブラウド一人という記載なので信頼できない。あくまで参考として挙げておこう。
Ellingtoniaでは、Saxes & Clarinetがマーシャル・ロイヤル(Marshall Royal)ではなく、オットー・ハードウィックとなっているだけで他は一致する。しかし上記パーソネルではアーサー・ウェッツェル、フレディ・ジェンキンスも在団していることになり、またベースも。ウェルマン・ブラウド一人という記載なので信頼できない。あくまで参考として挙げておこう。
しかしベースについて、右の写真は分かりにくいが、2ベース体制のエリントン楽団が出演している。ウェルマン・ブラウド(Wellman Braud)だけではないことは確かである。また2ベース体制のエリントン楽団の写真はあまりないので貴重である。
<Contents> … 「デューク・エリントン楽団 1929〜1943」(DVD JLD-410)&"Billie Holiday/Live and private recordings in Chronological order"(LDB01〜LDB22)
record1 A-1.[ビッグ・シティ・ブルース(サディスト・テイル)](Big city blues "Saddest tale")
上記本文中に詳述した。
[ここから有名なテディ・ウィルソンのブランズウィック・セッションへの参加となる。]
1935年に始まったテディ・ウィルソンのブランズウィック・セッションは、スイング時代の花形セッションと言われる。ともかく1935年からスタートする連続セッションは、1939年1月まで全133曲の吹込みを行うが、その音源が最も多く収録されているのは、ビリー・ホリデイのレコードである。

<Date&Place> … 1935年7月2日 ニューヨークにて録音
<Personnel> … テディ・ウィルソン・アンド・ヒズ・オーケストラ(Teddy Wilson and his Orchestra)
豪華な顔ぶれである。初登場はロイ・エルドリッジとコジー・コール。スイング時代最高のトランペット奏者と言われるロイ・エルドリッジの多分初レコーディングである。エルドリッジのディスコグラフィーでは、初録音は1936年2月5日自己名義のレコードとなっているが、それよりも半年早い。コジー・コールは、1930年ジェリー・ロール・モートンとのレコーディングがデビューだったようだが、そのレコードは持っていない。拙HPでは初である。
<Contents> … 「ビリー・ホリディ物語」(CBS SONY SOPH 61-62)
| record1-3. | 月に願いを | I wish on the moon |
| record1-4. | 月光のいたずら | What a little moonlight can do |
| record1-5. | ミス・ブラウンを貴方に | Miss Brown to you |
| record1-6. | 青のボンネット | A sunbonnet blue |
「ビリー・ホリディ物語」解説の大和昭氏は、「リズム隊の躍動感は見事であり、生き生きとした雰囲気に満ちている。エルドリッジの鋭さ、ウエブスターの豪快さ、グッドマンの軽妙さとフロント・ラインの3人が三者三様の素晴らしい出来を示している」と書いているが、確かにこれぞスイング時代最高のコンボ演奏の一つと言えると思う。
record1-3.[月に願いを]
もう一人の解説者、大橋巨泉氏は、初録音から2年がたち、ビリーもグッと落ち着きを見せるとし、グッドマンも未完成だが、トーンに色気があり、歌のバックもいい、この二人は恋仲だったかもしれないと書いている。確かに恋仲だったのであろう。それはビリー自身が自伝『奇妙な果実』(油井正一、大橋巨泉訳 晶文社)で明らかにしていることである。またラスト16小節をリードするエルドリッジは抜群である。
record1-4.[月光のいたずら]
軽快なテディのイントロに乗って出るBGのソロがいい。前半は中・低音を使い、後半は高音部でぐいぐいとスイングする。大和氏、巨泉氏ともBG最高のソロの一つとしているが確かに素晴らしい。この後のビリーの歌唱もまた素晴らしく、それにつられてかウエブスターも素晴らしい吹奏ぶりをしめす。
原曲の譜面を確認した巨泉氏は、全くつまらない流行歌をここまで名作に仕立て上げたのはこの面子だからであると述べている。
record1-5.[ミス・ブラウンを貴方に]
この曲でBGはイントロは高音で、メロディは中・低音でと展開を変えており、彼の好調ぶりを示している。ビリーとウエブスターが、レスターとのように溶け合っていないが、ウィルソン、エルドリッジが良くコールのブラシでのドラミングも素晴らしい。
record1-6.[青のボンネット]
この曲録音前になぜかBGは帰ってしまい、参加していないという。ウエブスター、エルドリッジの出来が素晴らしい。
余談
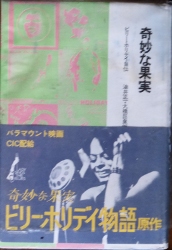 僕はどうしても気になることがある。以下は右ビリー・ホリディの自伝『奇妙な果実』(油井正一、大橋巨泉訳 晶文社)の次のくだりである。1973年に刊行された初版十刷ではP68〜69にかけての記述である。
僕はどうしても気になることがある。以下は右ビリー・ホリディの自伝『奇妙な果実』(油井正一、大橋巨泉訳 晶文社)の次のくだりである。1973年に刊行された初版十刷ではP68〜69にかけての記述である。
いつのころのことかは明確な記述はないが、
「毎朝仕事が終わってから、きっとどこかで大きなジャム・セッションがあった。ベニー・グッドマンやハリー・ジェイムスのようなミュージシャンもラジオの仕事が終わってからよく現れた。そして優秀な黒人、ロイ・エルドリッジ、レスター・ヤング、ベン・ウエブスターなどと一緒にジャムを楽しんだ。みんなが私の友達だったが、ベニー・グッドマンとの交際は特別の関係である。
私と彼は1週間に一度は、きっとこういうジャム・セッションの席で落ち合い、数時間を一緒に過ごしたが、ママはこの点では特に私に厳格で、白人の青年と一緒に歩き回ってはいけないと、くどいほど私に注意を与えた。
ベニーの姉のエセルは当時、彼のマネージャーをやっていた。彼女は、ベニーがきっとバンド・リーダーとして大物になるに違いないと目安を付けていたので、弟が黒い女と問題を起こして出世を棒に振ることを望まなかった。
ベニーは立派な男だった。絶対に退屈な男ではなかった。二人は一緒に過ごすために、ママや姉の裏をかいた。ベニーとの交際は私が別の恋愛に悩むようになるまで、相当長い間続いた。」
この後その別の恋愛のことに話題は移るのだが、ビリー曰く「二人は<いい仲>で、それは相当長い間続いた」と。しかしこのことについて触れた記述を他に見たことがない。
ベニー側の考えは姉の言う通り、「黒人女と問題を起こして出世を棒に振りたくない」という一点に尽きるであろう。そしてビリー側は、このことをあげつらって白人ジャズの王様、ベニー・グッドマン或いはその側近、さらに利害を共にするレコード会社などの連中に潰されたくないということでダンマリを決め込んだのだろうか?それとも単なるビリーの妄想であったのであろうか?
確かにこれは単なる男女のスキャンダルで音楽には関係ないという意見もあるかもしれない。それなら著名なジャズ評論家レナード・フェザー氏が、「彼(BG)は、意味深いことに、アリス(ジョン・ハモンド氏の妹)の誠実な夫であり、二人の娘たちの愛情深い父親であり、かつアリスが前の結婚でもうけた三人の子供たちの献身的な養父でもあった」というのも意味をなさないこととなる。
僕は、ビル・クロウがその著『さよなら、バードランド』に書くようにBGは自分のイメージ管理に最も腐心した男であったような気がする。最近で言われる『好感度』重視である。「良き夫であり、良き父親」であるというイメージがこの後彼の成功に大いに貢献したのではないかと思うのである。成功したミュージシャンが数多くの発表の機会を持ち、録音の機会を持つのは当然である。そして一面そうやってジャズの歴史は作られていったのである。

<Date & Place> … 1935年7月31日 ニューヨークにて録音
<Personnel> … テディ・ウィルソン・アンド・ヒズ・オーケストラ(Teddy Wilson and his orchestra)
<Contents> … 「ビリー・ホリディ物語 第1集」(CBS SONY SOPH 61-62)
| A面7. | こんな夜にこんな月なら | What a night , what a moon , what a girl |
| A面8. | 涙かくして街を行く | I'm painting the town red |
| A面9. | 燃えている私 | It's too hot for words |
2度目の録音は7月末に行われた。2度目のレコーディングは、さすがに2度目につき合わせるのは無理と判断されたのかクラリネットにはセシル・スコットが加わっている。ディスコグラフィーによれば、この日は全6曲の録音が行われたが、ビリー・ホリディが参加したのは3曲である。
そしてビリーの加わっていない3曲の内の1曲「スィート・ロレイン」のみが「ザ・テディ・ウィルソン」に収録されている。残り2曲、「ライザ」と「ロッゼッタ」であるが、「ライザ」はオクラ入りとなり、「ロッゼッタ」は未聴である。
まず、リーダーのウィルソン、ウエブスター、コールの3人はウィリー・ブライアント楽団からの参加で、セシル・スコットは35、6年当時ヘンリー・レッド・アレンのレコーディングに参加していたという。ジェファーソンは当時はフレッチャー・ヘンダーソンやチック・ウエッブの楽団でプレイしていた名手だという。
ビリーの加わった3曲に関して、解説の大和明氏は「ここでも取り上げられたナンバーは取るに足らない流行歌である」と述べ、さらに「『こんな夜にこんな月なら』も『涙かくして街を行く』も、最初のコーラスをアンサンブルとウィルソンのピアノで8小節或いは4小節ずつ交互に進行していくという構成が取られ、ウィルソンのプレイを引き立たせる工夫がされている。」
曲の解説はビリーの大ファンである故大橋巨泉氏が担当している。巨泉氏はここでもビリーをべた褒めで、演奏はコーニー(古臭い)がビリーだけは新しいとしている。僕はこの時代はまだスイングの爆発前夜であり、当時としてかなり高水準の演奏だと思うし、逆にビリーのかすれた声のはすっぱな歌い方が好きではない。「すれっからし」という言葉しか浮かんでこないが、自分に正直で「かまとと」ぶっていないところが良いという感想もあるだろうとは思う。
A-7.[こんな夜にこんな月なら]
ピアノがリードするアンサンブルが小気味よくスイングする。その後ビリーの歌が入り、ジェファーソン(As)、スコット(Cl)、ウィルソン(P)、エルドリッジ(Tp)、ウエブスター(Ts)と続き、再度スコットのリードするアンサンブルで終わる。顔見世的ナンバーだがそれなりに楽しいと僕は思う。
A-8.[涙かくして街を行く]
最初に触れたようにピアノとアンサンブルの交互の進行の後、短いAs、Tpソロの後歌が入る。ここでのヴォーカルは迫力がある。そしてそれを受けたエルドリッジのTpソロも素晴らしい。
A-9.[燃えている私]
タイトル通りかなり大胆で卑猥な内容で、ビリーのヴォーカルも何やら反抗的だとは巨泉氏。ヴォーカル後のAs、Cl、Ts、Tpと短いソロが続きその後はアンサンブルで締め括る。

<Date & Place> … 1935年10月25日 ニューヨークにて録音
<Personnel> … テディ・ウィルソン・アンド・ヒズ・オーケストラ(Teddy Wilson and his orchestra)
<Contents> … 「ビリー・ホリディ物語 第1集」(CBS SONY SOPH 61-62)
| B面1. | 日がな一日 | Twenty=four hours a day |
| B面2. | ヤンキーはショボかった | Yankee Doddle never went to town |
| B面3. | イーニー・ミーニー・マイニー・モー | Eeny meny miney mo |
| B面4. | 君を得たなら | If you were mine |
このセッションで注目されるのはテナー・サックスのチュー・ベリーで、同じホーキンズ派でも前回までのウエブスターは豪放さが持ち味だが、一方ベリーは豪快な中にもまろやかなソフト・トーンを持っているとは解説の大和氏。しかし前回までのウエブスターもそれほど豪放に吹いているわけではないと思うのだが。それにTbのベニー・モーテンもいい味を出していると思う。
B-1.[日がな一日]
いきなり出てくるチュー・ベリー、そしてモーテン、ウィルソン、エルドリッジなど短いが素晴らしいソロの連続である。曲は愚作で、ビリーもスイングしているものの手の施しようがないと巨泉氏は書くが、インストの素晴らしさで元は取れたと思うよ。
B-2.[ヤンキーはショボかった]
解説氏は、これも当時はやった凡庸な流行歌の一つであるが、ビリーの独特の遅れたノリが聴きもので、サビの終わりに例のヴィブラートを聴かせてくれるという。スケールの大きいモーテンのソロの方が聴きもののような気がするが。
B-3.[イーニー・ミーニー・マイニー・モー]
この曲は少し後の11月22日にヘレン・ウォードのヴォーカルでベニー・グッドマン楽団も録音している。当時の流行歌だったのだろうか?「これも愚曲の典型でビリーの誰も真似ることのできない「乗り」を楽しむしかない」とは巨泉氏。僕はモーテンとウィルソン、エルドリッジ、ベリーのソロ、及びバックのコールのドラミングなど素晴らしいので可。
B-4.[君を得たなら]
「トロンボーンのイントロを受けてのウィルソンのソロは、彼の生涯の最高の一つであろう。歌い方、乗り方、非の打ちようがない」とは巨泉氏。正確には「トロンボーンのイントロを受けて一瞬トロンボーンのつなぎがありヴォーカルの前の」ピアノ・ソロのことであろう。さらに氏は続けて「そしてああビリー!この限りない憧れをたたえた名唱をなんと表現したらいいのだろう。後半の「Yes」だけでも僕は胸があつくなる」と感極まっている。確かに熱演で内容も素晴らしいことは、僕にも分かる。
4度目のレコーディングは、12月の初めに行われた。全4曲が録音されたが、その内3曲にビリーが参加している。

<Date & Place> … 1935年12月3日 ニューヨークにて録音
<Personnel> … テディ・ウィルソン・アンド・ヒズ・オーケストラ(Teddy Wilson and his orchestra)
<Contents> … 「ビリー・ホリディ物語 第1集」(CBS SONY SOPH 61-62)
| B面5. | ジーズン・ザッツン・ゾーズ | These‘n’That‘n’those |
| B面6. | つき落されて | You let me down |
| B面7. | リズムまき散らし | Spleadi'n rhythm around |
解説大和明氏によれば、この日のセッションはエリントン楽団のジョニー・ホッジスに焦点を合わせるように行われたという。というのは他のフロント・ラインを構成するディック・クラーク、トム・メイシーというのはあまり名の知れたプレイヤーではないからであるという。
B-5.[ジーズン・ザッツン・ゾーズ]
ウィルソンのイントロからテーマを吹くホッジスはさすがの貫禄であると巨泉氏は書くが、確かに聴かせるアルトである。
B-6.[つき落されて]
ホッジスのドラマティックなソロを受けて歌い出すビリーは、抑えた歌唱が光っていると思う。ウィルソンのソロも良いが、バーバーのアコースティック・ギターでのソロは珍しいものであり、聴き応えもある。
B-7.[リズムまき散らし]
当時よくあったパターンの曲であるという。メイシーのClはグッドマンによく似ている。そして続くホッジスのソロも良いが、さらに続くクラークのTpソロはエルドリッジに比べると迫力がかけるのがよく分かるという。
このWebサイトについてのご意見、ご感想は、メールでお送りください。
お寄せいただいたご意見等は本文にて取り上げさせていただくことがあります。予めご了承ください。
 ビリーがどこで上映しているか知るためには私立探偵を雇う必要のあるような短編映画は「シンフォニー・イン・ブラック」("Symphony in black")というタイトルであり、右のデュークのDVDに収録されている。音楽は全篇エリントンが担当しているが、ビリーが出るのは僅かなシーンだけである。念のため映画の内容を簡単に記すと、
ビリーがどこで上映しているか知るためには私立探偵を雇う必要のあるような短編映画は「シンフォニー・イン・ブラック」("Symphony in black")というタイトルであり、右のデュークのDVDに収録されている。音楽は全篇エリントンが担当しているが、ビリーが出るのは僅かなシーンだけである。念のため映画の内容を簡単に記すと、 恋のトライアングル
恋のトライアングル ビリーのヴォーカルは相当崩しているので拍が把握しづらいがそこがうまさなのだろう、ビリーのアンニュイな歌い方が実に自然に聞こえる。また非常に抑えた表現で素晴らしい。確かに「感動的なブルース」と思う。短いが僕が今のところ最も気に入ったビリーのヴォーカルである。もっと歌って欲しかったな。
ビリーのヴォーカルは相当崩しているので拍が把握しづらいがそこがうまさなのだろう、ビリーのアンニュイな歌い方が実に自然に聞こえる。また非常に抑えた表現で素晴らしい。確かに「感動的なブルース」と思う。短いが僕が今のところ最も気に入ったビリーのヴォーカルである。もっと歌って欲しかったな。
![[Billie Holiday/Live and private recordings in Chronological order]ボックス](BillieHoliday_Chronologicalorder_2.jpg)
 Ellingtoniaでは、Saxes & Clarinetがマーシャル・ロイヤル(Marshall Royal)ではなく、オットー・ハードウィックとなっているだけで他は一致する。しかし上記パーソネルではアーサー・ウェッツェル、フレディ・ジェンキンスも在団していることになり、またベースも。ウェルマン・ブラウド一人という記載なので信頼できない。あくまで参考として挙げておこう。
Ellingtoniaでは、Saxes & Clarinetがマーシャル・ロイヤル(Marshall Royal)ではなく、オットー・ハードウィックとなっているだけで他は一致する。しかし上記パーソネルではアーサー・ウェッツェル、フレディ・ジェンキンスも在団していることになり、またベースも。ウェルマン・ブラウド一人という記載なので信頼できない。あくまで参考として挙げておこう。
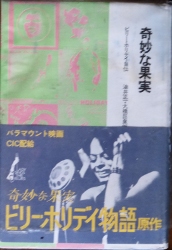 僕はどうしても気になることがある。以下は右ビリー・ホリディの自伝『奇妙な果実』(油井正一、大橋巨泉訳 晶文社)の次のくだりである。1973年に刊行された初版十刷ではP68〜69にかけての記述である。
僕はどうしても気になることがある。以下は右ビリー・ホリディの自伝『奇妙な果実』(油井正一、大橋巨泉訳 晶文社)の次のくだりである。1973年に刊行された初版十刷ではP68〜69にかけての記述である。

