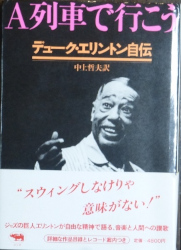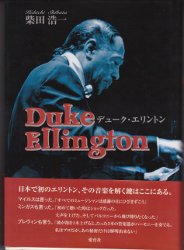デューク・エリントン 1931年
Duke Ellington 1931
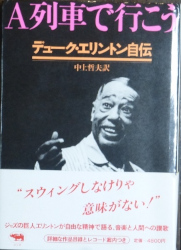
大恐慌が深刻化する1930年でもデューク・エリントンは、かなりのレコーディング数をこなしていた。しかし1931年になると録音数だけでいえばかなり数が減っていると言える。この1931年という年はエリントンとその楽団にとってはどんな年だったのだろう。
1930年後半に録音した「ムード・インディゴ」がヒットしていた。年間ヒット・チャートの第3位にランクされているので大ヒットと言える。母親が夕食を作るを待っている間の15分間に作ったというこの曲の反響についてはエリントン自身が『自伝』(P86)に書いている。
また、初めてシカゴのオリエンタル・シアターに出演した。この出演に当たって新たに女性シンガー、アイヴィー・アンダーソンを雇った。そして彼女を加えたメンバーでオリエンタル・シアターに2月13日から出演し劇場の新記録を作ったとあり、さらに3月13日に再び出演し自分の記録を更新したとある(『自伝』P126)。ただしこの年彼女を加えた録音はない。
<基本形Personnel>

<Date & Place> … Ellingtonia … 1931年1月10日ニューヨークにて録音 (RCA)
<Personnel> … ザ・ウーピー・メイカーズ (The whoopee makers)
基本形+Vocal … チック・ブロックChick Bullock
<Contents>
| CD10-15. | ゼム・ゼア・アイズ | Them there eyes |
| CD10-16. | ロッキン・チェア | Rockin’ chair |
| CD10-17. | アイム・ソー・イン・ラヴ・ウィズ・ユー | I’m so in love with you |
さて、デュークのこの年最初の録音は、Web版Ellingtoniaによれば、1月8日RCAにザ・ウーピー・メイカーズ名義で3曲録音が行われた。ところが2日後の1月10日に全く同じ曲をほぼ同じメンバーでRCAに再度録音している。
CDボックスHistoryに収録されているのは、1月10日のものである。ほぼ同じメンバーと書いたが異なっているのはヴォーカルだけで、8日のヴォーカルはシド・キャリー、10日はチック・ブロックとなっている。普通に考えれば、ヴォーカルに難ありと判断されたのだろう。因みにヴォーカル以外のメンバーは1930年11月の録音から変わっていない。
CD10-15「ゼム・ゼア・アイズ」は現在も演奏されたり歌われたりしているスタンダード・ナンバー。この4か月半後の4月29日にルイ・アームストロングも録音を行っているが、後にビリー・ホリディが歌って有名になったといわれている。ヴォーカルを挟むトランペット・ソロがよく歌っていて素晴らしい。
CD10-16「ロッキン・チェア」はホーギー・カーマイケル作のスタンダード・ナンバーで、こちらは逆にルイが先に1929年12月13日に録音している。
ルイのヴァージョンはどうしてもルイのヴォーカルが強力でアクが強い。まぁそれが売り物でもあるのだが、一方デュークのチック・ブロックは白人シンガーで、コットン・クラブという白人専用のクラブに専属出演していたエリントン楽団としては、こういった洗練路線を取っていくのは自然の流れだろう。ヴォーカル後のカーネィのBsソロが良い。
CD10-17.「アイム・ソー・イン・ラヴ・ウィズ・ユー」こちらはエリントンとミルズの共作で1930年11月8日録音の再録である。元々ヴォーカル入りのポップス路線の曲であるが、不況が深刻化する中、エリントンも当時流行のポップス・ヒット・チューンを取りがなければならなかったのであろう。

<Date & Place> … Ellingtonia、History…1931年1月14日ニューヨークにて録音 (Brunswick)
<Personnel> … ザ・ジャングル・バンド (The jungle band)
HistoryはPiano&Vocalにベニー・ペイン(Benny Paine)、Vocalにフランク・マーヴィン(Frank Marvin)が加わったとするが、EllingtoniaではVocalがチック・ブロックからベニー・ペイン(Benny Paine)に変わっただけであるとする。このヴォーカルがフランク・マーヴィンなのかベニー・ペインかは僕には分からないが、ピアノがエリントンから変わるということがあり得るだろうか?
<Contents>
| CD10-18. | ロッキン・チェア | Rockin’chair |
| CD10-19. | ロッキン・イン・リズム | Rockin’in rhythm |
| CD10-20. | 12番街のラグ | Twelfth street rag |
CD10-18.「ロッキン・チェア」この日の録音中唯一のヴォーカル・ナンバーで、4日前にチック・ブロックのヴォーカルで吹き込んだばかりだが、こちらブランズウィックには、ヴォーカルを変えて録音したということであろう。
CD10-19.「ロッキン・イン・リズム」エリントンの代表作の一つ。1930年11月に一度録音しているが、今回は2回目の録音となる。テンポが少し速めになった様な感じがする。
CD10-20.「12番街のラグ」ご存知「12番街のラグ」(Twelfth Street Rag)は1914年にユーディ・L・ボウマン(Euday L. Bowman)が作曲したラグタイム曲。1915年以前には確実に楽譜が発売されている。曲名はボウマンが出演していたカンザスシティの盛り場「12番街」から採られているという。ラグタイム時代にとりわけ有名なベスト・セラーとなった曲である。ルイ・アームストロングからレスター・ヤングまで、多くの様々なアーティスト達が録音してきていて、現在もディキシーランド・ジャズのスタンダード・ナンバーとなっている。
最もヒットしたのは、ピー・ウィー・ハント(Pee Wee Hunt)によるピアノ演奏で、この録音はビルボードの1948年のナンバー・ワン・シングルとなり、300万枚を超す売り上げとなったという。作曲者ユーディ・L・ボウマン自身もこの曲を録音しているという。エリントンの録音もバンド演奏としては、かなり早い時期ではなかったかと思う。
ベニー・ペイン…Pianoという表記で少々気になるところは、ペインはエリントン・バンドが不在の時にコットン・クラブに代役で出ていたキャブ・キャロウェイ・バンドのピアニストだったので、デュークと顔見知りでもおかしくない。しかしエリントンというピアニストがいるエリントン・バンドにピアニストとして加わるということがあり得るだろうか?と思って何度目か「12番街のラグ」を聴いていた時にハタと気が付いた。ここで披露されるピアノ・ソロはかなり音数が多い。もしかすると2人の連弾ではないかと。そういえばペインはファッツ・ウォーラーと連弾でレコードを吹き込んでいる男である。もし連弾とすればEllingtonia が誤りでHistoryが正しいことになる。

<Date & Place> … Ellingtonia、History…1931年1月14日ニューヨークにて録音
<Personnel> … バンド名不明
HistoryはPiano&Vocalにベニー・ペイン(Benny Paine)、Vocalにフランク・マーヴィン(Frank Marvin)とチック・ブロックChick Bullockの3人が加わったとする。Ellingtoniaではそもそも1月14日の録音はないことになっている。
<Contents>
| CD11-1. | 12番街のラグ | Twelfth street rag |
HistoryのCD11枚目最初の曲は「12番街のラグ」で録音日は1931年1月14日で、日付、パーソネルともCD10-20の「12番街のラグ」と同じである。しかし実際の演奏は異なる。こちらはアンサンブルの後すぐにピアノ・ソロとなり、しかも連弾だと思われる。そういった意味ではHistoryが正しいような気もするがなんと言っても信用できないのは、ヴォーカル自体が入っていないのである。この辺りは一体どうなっているのだろうか?

<Date & Place> … Ellingtonia、History…1931年1月16日ニューヨークにて録音 (RCA)
<Personnel> … デューク・エリントン・アンド・ヒズ・オーケストラ (Duke Ellington and his orchestra)
Historyでは、前録音と同じとするが、Ellingtoniaではヴォーカルがベニー・ペインからチック・ブロック(Chick Bullock)に変わったとする。
<Contents>
| CD11-2. | ロッキン・イン・リズム | Rockin’ in rhythm |
| CD11-3. | ザ・リヴァー・アンド・ミー | The river and me |
| CD11-4. | キープ・ア・ソング・イン・ユア・ソウル | Keep a song in your soul |
| CD11-5. | サム・アンド・デライラ | Sam and Delilah |
CD11-2.「 ロッキン・イン・リズム」は3度目の録音。大分洗練された演奏になってきた。
CD11-3.「ザ・リヴァー・アンド・ミー」は初登場の歌もの。
CD11-4.「キープ・ア・ソング・イン・ユア・ソウル」はファッツ・ウォーラーの作で、1930年フレッチャー・ヘンダーソン楽団が大傑作を吹き込んでいる。これも歌もの。「心に歌をもって元気に行こう」という感じの曲調のような気がする。
CD11-5.「サム・アンド・デライラ」はガーシュイン兄弟の作で初登場のような気がする。「サムソンとデリラ」のことであろう。

<Date & Place> … Ellingtonia、History…1931年1月20日 ニューヨークにて録音 (Brunswick)
<Personnel> … ザ・ジャングル・バンド (The jungle band)
Historyはチック・ブロックからフランク・マーヴィン(Frank Marvin)に変わったとするが、Ellingtoniaではヴォーカルがチック・ブロックからディック・ロバートソン(Dick Robertson)に変わったとしている。
<Contents>
| CD11-6. | ザ・ピーナッツ・ヴェンダー | The peanut vendor |
| CD11-7. | クレオール・ラプソディ― パート1 | Creole rhapsody part1 |
| CD11-8. | クレオール・ラプソディ― パート2 | Creole rhapsody part2 |
| CD11-9. | イズ・ザット・リリジョン | Is that religion ? |
CD11-6.「ザ・ピーナッツ・ヴェンダー」は邦題「南京豆売り」。有名なラテン・ナンバー。1930年12月にルイ・アームストロングがロスで吹き込んでいる。なかなか聴き応えがある。
CD11-7、8.の「クレオール・ラプソディ―」について次回録音(6月11日)と合わせて記載したい。
CD11-9.「イズ・ザット・リリジョン」ディック・ロバートソンあるいはフランク・マーヴィンのヴォーカル入り。短いナンバーでソロはほとんどない。
この後6月まで録音がない。巡業に出ていたのであろう。冒頭のシカゴのオリエンタル・シアターに出演したエピソードなどはこの間のものである。
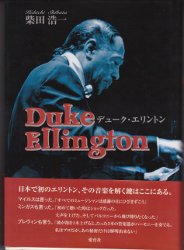
<Date & Place> … Ellingtonia、History…1931年6月11日ニュージャージー州キャムデンにて録音(RCA)
<Personnel> … デューク・エリントン・アンド・ヒズ・オーケストラ (Duke Ellington and his orchestra)
メンバーは、ブランク前1月20日と同じ
<Contents>
| CD11-10. | クレオール・ラプソディ― パート1 | Creole rhapsody part1 |
| CD11-11. | クレオール・ラプソディ― パート2 | Creole rhapsody part2 |
『デューク・エリントン』の作者柴田浩一氏は次のように述べる。「初めてSP片面の録音時間3分を超えた4分22秒の大曲」しかしこの4分22秒とは何であろう。
1月20日録音のクレオール・ラプソディ― パート1は、3分8秒、パート2は3分19秒、6月11日録音のクレオール・ラプソディ― パート1は、4分2秒、パート2は4分21秒である。時間でいうことではないが、演奏時間が最も近いのは6月11日録音の4分21秒である。
またこの曲はエリントンの中でも重要な位置を占める作品だと思う。不勉強で定かなことは言えないが、多分初めての組曲、ジャズ史上初めての組曲なのではないか?少なくともこれまで取り上げた中でこのように明確に組曲ですと言った曲はなかったと思う。
そしてこの曲は、最初の録音は1月で、次の録音は約半年後の6月である。この間録音がない。僕はどちらかと言えばあとの録音(RCA)の方が洗練度が増し、作品としては上かなと思っていた。さすがにガンサー・シュラー氏は詳細に解説しているが、それによると一般的には先の録音(Brunswick)の方が上という世評が多かったという。ではシュラー氏の解説を紹介しよう。
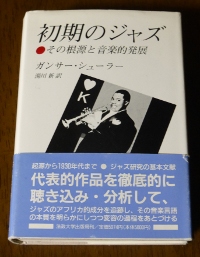 「エリントンは、自己のバンドという独特な表現手段を駆使する能力が向上するにつれて、その当初の用途からは独立した作品をますます創造できるようになった。このため彼の作品は時代を超えて生き延びた。飽くことのない音楽的探究心に駆られて、より大きな形式の問題に取り組んだ。1931年1月までに、彼は「クレオール・ラプソディ」の二つの版を創造した(Part1とPart2のことと思われる)。両者は半年の隔たりをおいて作曲されたが、二つの版を比較してみると、エリントンの手法がよく分かる。」 これはちょっと何を言っているのか分からない。
「エリントンは、自己のバンドという独特な表現手段を駆使する能力が向上するにつれて、その当初の用途からは独立した作品をますます創造できるようになった。このため彼の作品は時代を超えて生き延びた。飽くことのない音楽的探究心に駆られて、より大きな形式の問題に取り組んだ。1931年1月までに、彼は「クレオール・ラプソディ」の二つの版を創造した(Part1とPart2のことと思われる)。両者は半年の隔たりをおいて作曲されたが、二つの版を比較してみると、エリントンの手法がよく分かる。」 これはちょっと何を言っているのか分からない。
「私(シュラー氏)はヴィクターの第2の拡大された版の方が第1のブランズウィック版より出来映えが劣るという定評には賛同し難い。この曲は全体として形式面で一歩進んだ試みを行っているが、エリントンはそこで何よりもまず、非対称的長さの楽句とトロンボーンの二重奏(おそらくジャズでは最初の試み)を用い実験を行っているのである。
そして私(シュラー氏)はこの曲の第1版の演奏の大半が劣悪であることも指摘しなければならない。『オールド・マン・ブルース』の場合と異なり、この曲の形式がむやみやたらに錯綜しており、加えて集団的に創造されたヘッド・アレンジというよりはむしろエリントンの作曲という要素が多かったために、奏者たちの演奏が落ち着かず硬直しているし、エリントン自身の古めかしいピアノの間奏(幸いなことに、第2版では変更されて、最小限にまで縮小されている)が曲を一層不連続なものとしている。更には、不均等な作曲素材の組み合わせと終始同一なテンポの演奏とが全く合致していなかった。2つの版の間に経過した半年の歳月で、エリントンはこのことを理解したに違いない。というのは、ヴィクターの演奏では、それぞれのセクションを異なるテンポで演奏している。と言って作曲が改善されているわけではないのだが、その演奏が改善されたことは確かである。当然のことながら、その間に、バンドがこの曲を演奏できるようになったことが明らかなのである。アンサンブル奏の部分は比較にならないほどに改善され、テンポの変化はージャズの世界では当時も今日でもまれなことであるが―驚異的なまでに巧みに演奏される。ソロもまた目立ってというほどでもないが前よりも優秀である。
さらに第1版の裏面はほとんど全部が第2版では破棄され、『ムード・インディゴ』の夢見るような、抒情的な旋律を用いた追加の素材に差し替えられた。これによってエリントンとしては初めての3部形式の曲となった。この新しいセクションは賑やかな変奏曲の形式で書かれている。まずは、アーサー・ホエッツェルがこれを彼独特なやり方で演奏し、次いでサキソフォンとミュート付きのヴァルヴ・トロンボーン(ティゾル)のとてつもなく滑らかな混合音へと受け継がれ、最後はビガードとデュークによってフリー・テンポで演奏される。ホエッツェルを伴奏する3本のサキソフォンは、音色と声部進行の観点から見ると、エリントンが1940年の華やかな傑作“Warm valley”や「月のもや(?)」、“Dusk”においてはじめて接近した響きを実現している。
「クレオール・ラプソディ」の第2版においては、すでに拡大された形式をさらに拡大することがエリントンにとって過大な負担であることが判明する。ガーシュインの「ラプソディー・イン・ブルー」からの些細な借用にもかかわらず、おそらくはそのためにかえって最後の辻褄がピッタリとはあっていない。こうした判断の誤りはあっても、ヴィクターの演奏の大部分は改良されていることには違いないし、エリントンが「クレオール・ラプソディ―」の体験からじっくり学んだことを後期の作品で活用したことは明らかである。」

<Date & Place> … Ellingtonia、History…1931年6月16、17日ニュージャージー州キャムデンにて録音(RCA)
<Personnel> … デューク・エリントン・アンド・ヒズ・オーケストラ (Duke Ellington and his orchestra)
同前。
<Contents>
| CD11-12. | ライムハウス・ブルース | Limehouse blues | 6月16日 |
| CD11-13. | エコーズ・オブ・ザ・ジャングル | Echoes of the jungle | 6月16日 |
| CD11-14. | イッツ・グローリー | It’s glory | 6月17日 |
| CD11-15. | ザ・ミステリー・ソング | The mystery song | 6月17日 |
グッとエリントン・サウンドらしくなってくるが、ここでもシュラー氏が詳細な解説をしているので以下紹介しよう。
「エリントンは、『クレオール・ラプソディ―』において異例な実験をこっそりやってから、エリントンはより型にはまったジャズの分野に復帰した。エリントン楽団は、その前の時期には例年50数面分の録音を行ったのに、まことに対照的なことだが、1931年には「ライムハウス・ブルース(Limehouse blues)」、「ジャングルの轟(Echoes of jungle)」、「イッツ・グローリー(It’s glory)」、「ザ・ミステリー・ソング(The mystery song)」とわずか4面分の録音しか行わなかった(? 1月にも録音を行っていることをお忘れか)。この4曲全てがこの「修行」時代の頂点をあらわすのみならず、整理と洗練の長い期間の始まりでもあった。1931年のこれらの4面の作品の中に、1940−42年の偉大なエリントン時代の基本的な響きと手法が表れていたのである。彼のスタイルはすでに十分な個性があって、わずかな成長で、若さが円熟した表現に転化する気配であった。
1931年のこうした作品は「作曲された」作品のカテゴリーに属する。それらの中で最も限界を持つものがCD11-14.「イッツ・グローリー」であった。というのは、時代遅れのダンスのリズムとスラップ・ベースが作曲作品としての価値を損なうところがったからである。しかしながら、ブラスとリードの書法―豊かな8声部の融合する響き―が優れていた、我々は、基本的には編曲されたコーラスを聴いているということをほとんど忘れてしまうほどである。おまけにこのレコードには二つの感興に富む瞬間が含まれている。第1は、第2コーラスのブリッジの箇所で登場する。ナントンが、2本の低音域のクラリネットとミュート付きのヴァルヴ・トロンボーンのトリオに伴奏されて、微妙なワウワウ音を使い、リードのパートを演奏し、それによって1931年に音楽家たちを驚愕させたに違いないし、今日ですら完璧に新鮮で蠱惑的に響きもする「ブルーな」音を創り出した箇所である。もう一つの素晴らしい瞬間は次のコーラスで、クーティー・ウィリアムスのソロの背後で柔らかな「うねる」サックスの音型を再び採用した箇所で発生する。
CD11-12.「ライムハウス・ブルース」
エリントンの作曲上の才能は1931年ではすでに十分に成長していた。他人の作品―ありふれたスタンダード曲―を全くエリントン的な作品にまで変形することすらやってのけた。かくて今曲では当時の他のどのバンドの響きとも混同できない響きを我々は耳にする。ブラスが煌めくような豊かな響きを出し、その対照としてCD11-14.「イッツ・グローリー」において遭遇したばかりのブルーな音の組み合わせがここでも提示される。エリントンは懸命にも露骨な東洋主義(この曲を演奏する他のすべてのバンドが使ったし、エリントン自身もまた以前“Japanese dream”では使いもしたピアノによる5音階のチリンチリンという響き)を抑制している。垂直的な2ビートのリズムだけがこのレコードを堅苦しいものにしているのだが、それにしても、アンサンブルの楽句での流れるような水平的なメロディー・ラインの動きで充分相殺されている。
CD11-13.「エコーズ・オブ・ザ・ジャングル」
この曲は、おそらくはクーティー・ウィリアムスによって書かれたもので、コットン・クラブの客たちに暗黒アフリカを垣間見せるために作られた舞台向けの曲として登場したに違いない。しかしながら、英国の作家チャールズ・フォックスが指摘した通り、これは「逆説的なまでに極度に洗練された」作品だった。優れた演奏に支えられて、不滅の独創性を備えたこの作品は、これらの4曲の中で最も古臭くない―事実、1931年の場合と同じくらいに今日でも新鮮であり、時間を超越したところがある。この曲の場合にも、信じがたく豊かなブラスの響き、この場合にはホッジスの開放的なアルトの音で和らげられ、装飾された轟音に我々は驚嘆させられてしまう。クーティーのソロの出番は2回あって、始めは官能的なしつこさを込めて開放音で、次いではプランジャー・ミュートを付けて、彼の最も想像力に富む即興の一つとして登場する。彼の背後では、ここでも半音階的な、転がるようなサキソフォンの音型―エリントンが決して飽きることがないように見える楽器の組み合わせ―をここでも耳にすることができる。これに続く経過的な楽句は低音域のビガードを前面に押し出して、それにフレディ・ガイのバンジョーの方型温のグリッサンドが応答するのだが、これは嵐の前の静けさのようなものだ。そして最後の3小節でエリントンは、「ココ」の最終コーラスを先取りするビッグ・バンドの響きと和音を創り出す。
1931年6月にコットン・クラブに居合わせなかったとすれば、いかなる舞台装置やパフォーマンスがCD11-15.「ザ・ミステリー・ソング」の冒頭部の魔術的雰囲気に刺激を与えたのか、頭の中で想像することは困難である。全くありきたりのピアノの導入部が突然霊感溢れる響き、単なる物真似ならいざ知らず、複製することも、模倣することもおよそ不可能な余りに独創的な瞬間へと転化する。持続する和音、彼方から聴こえてくるミュートの付けられた音色、ガイの不安を煽るようないささか緊迫したバンジョーの音などが混ざり合って、忘れがたい響きを醸し出す。残念ながら冒頭部を過ぎると、エリントンはこの水準の霊感を維持できなかった(これは音楽がダンスの定型的仕草と結びついていたという機能的な理由のためであったのかもしれない)。いずれにしてもこの輝かしい冒頭の後は、どの部分も高揚感が欠けていて月並みである。エリントンがこの霊感溢れる断片に対して、それにふさわしい形式枠組みを与えなかったのは残念なことである。
HistoryのCD11枚目はここでも取り上げたように、1931年1月から1932年2月までの録音を取り上げている。僕は何気にこのCDを聴いていて驚くことは、最初は「ああ、初期のエリントンだなぁ」と思うのだが、最後に近づくにつれて本来のエリントン(僕の思う本来のエリントンは最初に聴いた1940年前後の録音)にほぼ近いということである。つまりこの時期エリントンはそのサウンドの完成期に向けてグングンと進んでいたことを示している。恐るべしエリントン!今後の作品がますます楽しみになる。
このWebサイトについてのご意見、ご感想は、メールでお送りください。
お寄せいただいたご意見等は本文にて取り上げさせていただくことがあります。予めご了承ください。
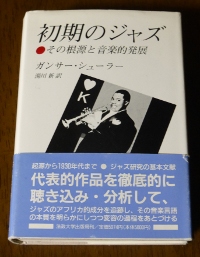 「エリントンは、自己のバンドという独特な表現手段を駆使する能力が向上するにつれて、その当初の用途からは独立した作品をますます創造できるようになった。このため彼の作品は時代を超えて生き延びた。飽くことのない音楽的探究心に駆られて、より大きな形式の問題に取り組んだ。1931年1月までに、彼は「クレオール・ラプソディ」の二つの版を創造した(Part1とPart2のことと思われる)。両者は半年の隔たりをおいて作曲されたが、二つの版を比較してみると、エリントンの手法がよく分かる。」 これはちょっと何を言っているのか分からない。
「エリントンは、自己のバンドという独特な表現手段を駆使する能力が向上するにつれて、その当初の用途からは独立した作品をますます創造できるようになった。このため彼の作品は時代を超えて生き延びた。飽くことのない音楽的探究心に駆られて、より大きな形式の問題に取り組んだ。1931年1月までに、彼は「クレオール・ラプソディ」の二つの版を創造した(Part1とPart2のことと思われる)。両者は半年の隔たりをおいて作曲されたが、二つの版を比較してみると、エリントンの手法がよく分かる。」 これはちょっと何を言っているのか分からない。