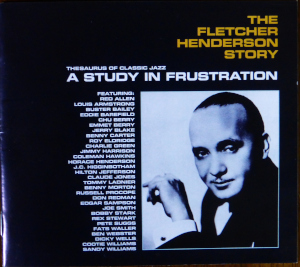
師粟村政昭氏は、「膨大な数のフレッチャー・ヘンダーソンのバンドの吹込みの中で〜(全文はフレッチャー・ヘンダーソン・プロフィール参照)」と書いているが、僕は余りフレッチャー・ヘンダーソンのレコードを売っているのを見たことが無い、特に最近は。僕がジャズを聴きはじめたころ、ジャズ・ファンである限り所有するのが必須のレコードと言われるレコードが何枚かありそのうちの1枚が「フレッチャー・ヘンダーソン/スタディ・イン・フラストレイション」であった。4枚組の大作で値段も高かった。その頃で記憶しているヘンダーソンのレコードはそのくらいである。そしてそれは高校生が簡単に買えるものではなくいずれ大人になったらと思っていたら、自分がジャズから離れてしまい買いそびれてしまった。そして何年か前、今回ご紹介する“The Fletcher Henderson story / A study in frustration”CD3枚組を見つけ購入した。
元々のレコードを知らないので完全復活CDなのかどうかは判断しようがない。しかし、CD購入とどちらが先か忘れてしまったが、中古レコード・ショップで「CBS・フェイバリット・ジャズ 100」シリーズの1枚として発売された「フレッチャー・ヘンダーソンの肖像」(CBS 20AP-1428)というLPを購入した。
このアルバムは、「スタディ・イン・フラストレイション」から選りすぐりの16曲を1枚のLPにまとめたもので。そのライナー・ノート(故油井正一氏が担当)によるともともとの「スタディ・イン・フラストレイション」4枚組には全64曲が収録されていると記されている。

一方CD版には全74曲が収録されている。CDのライナー・ノートを概観すると多分完全復活盤のようではあるけれど、プラス10曲ほど多いのか入れ替えがあるのかということになる。
ともかく今後もし中古のレコード・ショップで「フレッチャー・ヘンダーソン/スタディ・イン・フラストレイション」4枚組レコードを見つけたら、特に解説付きの日本盤を見つけたら、そして余り高くなければ絶対購入したいと思っている。
「スタディ・イン・フラストレイション(A study in frustration)」とはすごいタイトルだ。CDセットにはジョン・ハモンド氏によるオリジナルのライナー・ノートが載っている。どうもそれによると正式なタイトルは「フレッチャー・ヘンダーソン物語(The Fletcher Henderson story)」で副題が「スタディ・イン・フラストレイション(A study in frustration)」ということのようだ。“フラストレイション(Frustration)”という言葉は最近ではほぼ日本でも定着している。<挫折>、<憤懣>、<欲求不満>というような意味で、「フラストレイションが溜まる」などと普通に使われるが、昔、僕が高校生のころは聞いたことが無かった。
要はベニー・グッドマンを売出し、カウント・ベイシー、チャーリー・クリスチャン、ビリー・ホリディといった後世のジャズに大きな影響を及ぼしたジャズ界の大立者ジョン・ハモンド氏がフレッチャー・ヘンダーソンの吹込みを世に出すために整理・編集作業を終えた時副題に“A study in frustration”と付けざるを得なかった、この作業は「挫折の研究」あるいは「欲求不満の研究」であった、と思わざるを得なかったということであろう。
1961年に書かれたオリジナル・ライナー・ノートは以下のように締めくくられている。下手くそな訳で申し訳ないが、いや下手なだけではなく間違っているかもしれないが、「1920年代、フレッチャー・ヘンダーソンのオーケストラは最も進歩的なバンドであったがごく限られた人々にしか知られていなかった。彼は頑張っているミュージシャンに多大な栄誉を受けられるように世に送り出し、30・40年代にベニー・グッドマンを「キング・オブ・スイング」の座に就ける優れた編曲を考案した。彼は自身の作曲した作品の偉大なレコーディングを行ったが、売れ行きは良くなかった。しかし同じ曲を同じ編曲で吹込みしたベニー・グッドマンのレコードは天文学的数字の売れ行きを記録した。このことは明白な事実である。彼は憤懣やる方なかった。」
ヘンダーソンは30年代初期にBGのアレンジャーとなるが、何度か自分のバンドを再起する。しかし経営が立ち行かなくなりまたBGの下に戻るのである。映画「ベニー・グッドマン物語」にフレッチャー・ヘンダーソンは実名で出演している。そこは映画なので、にこやかにBGと握手を交わし、会話を交わしているが彼の本当の心中はどのようなものであったろう。
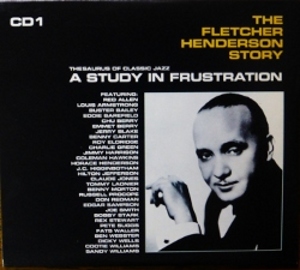
| Bandleader & Piano | … | フレッチャー・ヘンダーソン | Fletcher Henderson |
| Cornet | … | エルマー・チェンバース | Elmer Chambers |
| Trombone | … | テディ・ニクソン | Teddy Nixon |
| Clarinet & Alto sax | … | ドン・レッドマン | Don Redman |
| Clarinet , Tenor , Alto & Bass sax | … | コールマン・ホーキンス | Coleman Hawkins |
| Banjo | … | チャーリー・ディクソン | Charlie Dixon |

CD1-1.ザ・ディクティ・ブルース(The dicty blues)
ドイツが生んだ世界的なジャズ評論家ヨアヒム・ベーレントは、ビッグ・バンドがいつごろ始まったかを確かめることは難しいとしながら、ニューオリンズでジャズが始まった次の瞬間ビッグ・バンド・ジャズが起こりスイング時代へと続くとしている。そしてフレッチャー・ヘンダーソンの楽団がその過渡期をはっきり示している。ビッグ・バンド・ジャズの歴史はヘンダーソンと共に始まったと書いている。それを証明するように今回取り上げた1923年の録音は6人編成でありとてもビッグ・バンドと呼べる編成ではないのだが、2曲目翌1924年の吹込みでは4人増えて10人体制となっていると概要を解説している。
そしてこの録音については、ガンサー・シュラー氏はルイ・アームストロング加入前のヘンダーソン楽団の演奏の例としてその著「初期のジャズ」で取り上げている。
フレッチャーの作でドン・レッドマンによる編曲。ドン・レッドマンは幼時から神童として誉れが高く当初からバンドの音楽監督的位置についていた。ヘンダーソンのバンドのレパートリーの大半は、当時のヒット曲や出来合いの編曲で構成されていたが、レッドマンは少しずつ、出来合いの編曲を作り直したり、フレッチャーの作った曲を編曲し直したりし始めていた。この曲はそういったレッドマンの新しい試みが出始めている曲だとして詳しい分析を行っている。
即興のアンサンブル、和声的な伴奏つきの(あるいはなしの)ソロ、そして単純なソロ風の楽句が和声を付けられてさらに単純なリフの音型と対置される両者の結合形でもって構成される。これらの組み合わせ全ての中で、リードとブラスのセクションは対照的な演奏を行う。
リードはやや静的であまり変化しない和声を、ブラスは動きが派手なアンサンブルの楽句を奏する。オーケストレイションが実に多彩で、コールマン・ホーキンスのサキソフォンに多様な役割が与えられる。彼は内声部の和声パート、即興の対旋律、ソロを受け持ち時にはチューバまで掛け持ちして、ブギウギ風なベース・ラインを奏することさえある。
また当時は大変高級なものとされていた高い音程のチャイム音の短い挿入があるが、これは当時洗練された白人バンドによって広く使われた手法であったという。タイトルの<dicty>とは「高級な」とか「紳士気取りの」というような意味なので、その辺りの雰囲気を出すために使ったのだろう。
リズム上の節回しの点では、音をきっちりビートに乗せるので、どうしても断続的になり、ホーキンスの攻撃的なスラップ・タンギング奏法と結びつくと今日では理解しにくい響きを起こしている。8分音符はほとんど符点8分音符―16分音符のように演奏され、レガート奏法はほとんど行われない。こうしたリズム上の様式要素は、初期のバンドの地域的特徴を記述するうえで大変重要であるとしている。
かなり詳細だが、よく分からない。ごく初期のコールマン・ホーキンスのソロが聴けるし、クラリネット・ソロはレッドマンだろう。この二人は後にルイ・アームストロングと出会うことで飛躍していくがその前のプレイが聴ける貴重な音源である。
このWebサイトについてのご意見、ご感想は、メールでお送りください。
お寄せいただいたご意見等は本文にて取り上げさせていただくことがあります。予めご了承ください。