
人はデューク・エリントンというと何を連想するだろうか?僕は壮大な「お城」を思い浮かべてしまう。よく彼はルイ・アームストロングやチャーリー・パーカーのようなジャズのスタイルの変革者ではないと言われる。僕もそう思う。彼はひとえに自分の「城」を築いてきたのだと思う。ひたすら自分の感性と創造性を磨き、信じ一心に自分の世界、「城」を築いてきたのだと思う。
人はその果てしない創造力、ひたむきさ、そしてその作品の美しさ、力強さ、深淵さに感動するのであろう。彼の作り上げた「城」はとてつもなく壮大である。限りなく広くそして深い。さぁ、ゆっくりとじっくりとその美しさを味わっていこう。
そんなデュークの活動を録音として味わうことができる最初の年がこの1924年なのである。
全てにおいて優雅でゆとりを感じさせる、だからこそ”Duke”なのだが、そんな彼も最初から何もかにもがうまく行ったわけではない。エリントンは生まれた町ワシントンで音楽活動を開始しバンドを結成する。それはそれなりにうまく行っていたようだが、より一層の刺激を求めて1922年バンドとニュー・ヨークに上るのだが、彼らの演奏は全くの不評で、食うや食わずほうほうの体でワシントンに舞い戻るである。しかし翌1923年4月ピアニストのファッツ・ウォーラーの勧めで再度ニュー・ヨークに上るのである。
この2度目のニュー・ヨーク進出でも最初はなかなかうまく仕事が決まらず苦労したようだが、知り合いたちの助けで徐々に仕事を得ることができるようになるのである。
そしてデュークの初録音となるのだが、それはバンドではなくそのピアノの腕を買われたものであった。
![[デューク・エリントン・BYGレコード・ジャケット]](DukeEllington_BYG.jpg)
| Vocal | … | アルバータ・ハンター | Alberta Hunter |
| Piano | … | デューク・エリントン | Duke Ellington |
| A面2. | イッツ・ゴナ・ビー・ア・コールド・ウィンター | It's gonna be a cold winter |
| A面3. | パーラー・ソーシャル・デラックス | Parlor social de lux |
我らがデューク・エリントンの初録音は1924年11月とされる。”Ellingtonia”のdiscographyに記載も同様である。柴田浩一氏の著作『デューク・エリントン』によると、『女性ブルース・シンガーであるアルバータ・ハンター(Alberta Hunter)のレコーディングにソニー・グリアーと参加した』とある。
問題が2つある。1つ目はこのレコーディング・データ(BYG盤のデータ及びEllingtonia)を見るとソニー・グリアーの参加は記載されていない。
2つ目は、BYG盤の裏のPersonnel及びEllingtoniaのデータには、女性歌手を”Alberta Hunter”ではなく”Alberta Prime”と記載していることである。こちらについては”Encyclopedia of the Harlem renaissance”によると、「アルバータ・ハンターは、1924年アルバータ・プライム(Alberta Prime)という名前でデューク・エリントンとレコーディングを行った」とあるので、このような変名を使ったということであろう。
「アルバータ・ハンター」は、女性ヴォードヴィル・シンガーの草分け的存在としてこれまでも名前が登場している。彼女が作曲し自身でも吹き込んだ「ダウンハーテッド・ブルース」はベッシー・スミスによって歌われ大ヒットしている。
当然のことだが、どちらも非常に音が悪い。残っていたSP盤から音を採録したものと思われる。アルバータ・ハンターは1895年生まれでデュークの先輩格、この当時は彼女の方が名が売れていた。そこに呼ばれたという格好なのだろう。とはいっても彼女もまだ30歳くらい。聴いてみると声が若いのにびっくりする。
イッツ・ゴナ・ビー・ア・コールド・ウィンター
録音状態はひどい。速くなったり遅くなったりする。曲はブルースではない。ハンターのヴォーカルのバックを無難にこなしたという感じである。
パーラー・ソーシャル・デラックス
男性の歌との掛け合いのように進行し、2人でコーラスを取る個所もある。どちらかというと男の方の出番が多い。このころソニー・グリアーはヴォーカルも担当していたので、このヴォーカルがグリアーだろう。効果音的に叩き物の音もするので、それもグリアーだと思う。こちらの作曲は「Trent-Mills-Ellington」となっている。
アルバータ・ハンターは1957年歌手を引退し看護婦となったが、デュークの没後1977年に85歳でカムバックし周囲を驚かせた。カムバック後の映像はYoutubeに載っている。
こういうレコードは聴いてそれほど面白いものではないが、ミーハーの僕には興味深いレコードだ。

左の写真はザ・ワシントニアンズの写真。左からソニー・グリア、チャーリー・アーヴィス、ババー・マイレイ、エルマー・スノウデン、オットー・ハードウィック、デューク。1924年に退団したスノウデンが写っているの24年前半に写したものと思う。
| Bandleader & Piano | … | デューク・エリントン | Duke Ellington |
| Cornet | … | ババー・マイレイ | Bubber Miley |
| Trombone | … | チャーリー・アーヴィス | Charlie Irvis |
| Saxes | … | オットー・ハードウィック | Otto Hardwick |
| Guitar | … | フレッド・ガイ | Fred Guy |
| Drums | … | ソニー・グリアー | Sonny Greer |

| A面4. | チュー・チュー | Choo Choo |
| A面5. | レイニー・ナイツ | Rainy nights |
まず音源について気になる表記として、”The Duke”はドイツのHistory社が編集・販売しているものでエリントン・ファンにはおなじみにCDセット。CD40枚組のボックスで、不備は指摘されているものの1924〜1947年までの音源はかなりの確率で揃う優れもの。これからしばらくはこのセットにお世話になることと思う。
メンバーについて、バンジョーを担当している奏者History社のCDのデータによればフレッド・ガイとなっているが、Ellingtoniaではジョージ・フランシス(George Francis)となっているのである。色々な記載を見るとこの吹込みでは、フレッド・ガイという記載とジョージ・フランシスという記載があり判然としないという。しかしこのジョージ・フランシスという人物の記事はほとんど見られず謎の人物ではある。
| Vocal | … | ジョー・トレント | Jo Trent |
| Trombone | … | チャーリー・アーヴィス | Charlie Irvis |
| Saxes | … | オットー・ハードウィック | Otto Hardwick |
| Piano | … | デューク・エリントン | Duke Ellington |
| Guitar | … | フレッド・ガイ | Fred Guy |
| Drums | … | ソニー・グリアー | Sonny Greer |
| Vocal & Drums | … | ソニー・グリアー | Sonny Greer |
| Trombone | … | チャーリー・アーヴィス | Charlie Irvis |
| Saxes | … | オットー・ハードウィック | Otto Hardwick |
| Piano | … | デューク・エリントン | Duke Ellington |
| Guitar | … | フレッド・ガイ | Fred Guy |
| A面6. | ディーコン・ジャズ | Deacon jazz |
| A面7. | オー・ハウ・アイ・ラヴ・マイ・ダーリン | Oh,how I love my darling |
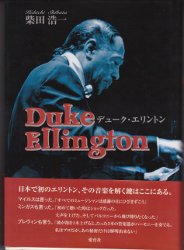
BYG盤A面4〜7は1924年11月録音とあるだけだが、Ellingtoniaのディスコグラフィーでは、同一セッションとしている。A面6〜7の2曲はHistoryには収録されていないがEllingtoniaには記載している。『デューク・エリントン』の著者柴田氏はフレッド・ガイをギターとしているが、音を聞く限りバンジョーと思われる。
また柴田氏は「1924年25歳という年を考慮したとしても特別優れた作曲とは言い難いし、デュークでなくても書けただろう。強いて挙げれば、”Choo Choo”では、曲の終わりに後にずっと使うようになる汽車の擬音を用い、”Rainy nights”では得意のもの憂い雰囲気が現れている。」とした上で、「それよりもここでは、ババー、チャーリー、オットー等のソロが素晴らしい。この時期他のバンドはアンサンブルを主体にしていることから考えると、この2曲も個人技を重視した。特別のものに思えてくる」と評価している。
この4曲ともドラマーにソニー・グリアーが参加しているがドラムの音はほとんど聞き取れない。リズムをリードするのはバンジョーである。誰がバンジョーを弾いているか僕には決め手がないが、後のガイとは違いかなり前面に出てプレイしている。明らかにニューオリンズ・スタイルと違うのは、ヒョロヒョロとのべつまくなく吹かれるクラリネットのオブリガードが無く、トロンボーンもテイル・ゲート・スタイルではないことである。デュークのピアノはやはりラグ・タイム的である。後にはアンサンブル要員的になるオットー・ハードウィックも素晴らしいソロを取る。
ガンサー・シュラー氏は[A面4.チュー・チュー]と[A面5.レイニー・ナイツ]を1926年の録音として一部譜例付きで詳細に解説している。この2曲はEllingtoniaのディスコグラフィーでも、History盤CDセットの録音データでも、BYG盤のレコード記載のデータでも一様に1924年11月録音と記載されている。多数決というわけではないが、この2面分は1924年11月の録音としておくが、参考のためシュラー氏の解説を付記しておきたい。<
![[Choo choo]譜例](ChooChoo_furei_1.jpg)
A面4.チュー・チュー
<Choo Choo>とは、蒸気機関車の発する音の擬音化だそうで、すぐに思い出すのはニール・セダカ(オジサンはExileとは思わないのだ)の「恋の片道切符」、”Choo choo train a-chugigin' down the track 〜”と失恋ソングとは思えない軽快な出だしで始まる曲があるので汽車にちなんだ曲であることは推測がつく。因みにこの曲は日本で大ヒットしたがヒットしたのは日本だけだそうです。
マイレイ、ハードウィック、バンジョーのソロがあり、マイレイのリードするテーマに戻り汽車の擬音で締めくくる。
シュラー氏「全体の出来映えから見ると最初期の中で最良である。これは格好のよいコード進行が付けられたエリントンの曲で、この進行に乗って、マイレイが原旋律に密着した、無防備にまでに単純な「言い換え的ソロ」を展開する。「言い換え的ソロ」とは、フランスの評論家アンドレ・オデールが用いた用語で、原曲の旋律線の潤色や装飾に基本的に依拠している類のソロということ。ソロの随所に、陽気で郷愁をそそる味付けが施され、プランジャーとグロウルの技法の使い方はごく控え目である(右譜例)。この曲は、予想されるようにグリアの手さばきで繰り出されるお定まりの列車の汽笛音で終止する」
A面5.レイニー・ナイツ
ハードウィックがテーマをリードする。細かく打ち震えるようなヴィブラートを聞かせたソロで、後のジョニー・ホッジスを彷彿とさせる。年代的にはホッジスが影響を受けたのではないか。アーヴィスのトロンボーン・ソロもやわらかで曲調に合っていい。マイレイのミュートによるソロもグロウルでなくても、聴かせるソロを取れることを証明するようなソロだ。
シュラー氏「最初の3小節にくだんのコード進行[B♭⇒G♭7⇒B♭⇒B♭7]が登場し、アーヴィスとマイレイのそれぞれ丸1コーラス分の、双方とも原旋律の言い換え的即興が含まれている。アーヴィスのソロは伸び伸びして音が大きく基本的に単純で、時として大変優しい。どちらのソロの背後でも、リズム・セクションは、各小節の2拍目と4拍目でコードを刻み、1拍目と3拍目では全く刻まないから、このセクション全体がどこかもたついて、間延びした印象を与える。このレコードはナインス・コードで終わるのだが、セヴンス・コードの終止が使われ過ぎて迫力が亡くなり始めた後、1920年代中頃に”ヒップ”となった手法である。」
A面6.ディーコン・ジャズ
Deaconとは、教会の執事というような意味で、確かオットー・ハードウィックの仇名だったような気がします。違っていたら訂正します。ソロはハードウィック⇒デューク⇒マイレイと続く。ハードウィックはこの4曲はクラリネットを吹いていないと思う。打楽器的な奏法も見せ面白い味を出している。
A面7.オー・ハウ・アイ・ラヴ・マイ・ダーリン
これはグリアーのヴォーカル、エンターテイメント性を前面に押し出した作品。ソロもハードウィックが大活躍だ。デュークもソロを取るが、やはりラグ・タイム調である。
このWebサイトについてのご意見、ご感想は、メールでお送りください。
お寄せいただいたご意見等は本文にて取り上げさせていただくことがあります。予めご了承ください。